〈原子核反応の統一理論モデル〉
原子核反応の統一理論モデル 1
A Unified Theory Model for Nuclear Reaction
2003、 5、 11
A 核反応概論
① はじめに
ここ10年間の低温核融合実験から固体内核反応の研究が進展し、近年では低エネルギーレベルでの核融合もしくは核変換に関する実験報告が相次ぎ、低温核反応に対する関心が急速に高まりつつある事は承知の通りである。今や原子核に膨大なエネルギーを付加しなくても、僅かなエネルギーで核融合や核崩壊が起きる事は常識となっており、従来の核物理論が通用しない段階に到ったと言って良いかもしれない。
例えば、金属固体内に吸蔵された重水素原子核が互いに融合して一連の重合体を形成し、それが核崩壊を起こして低質量の核生成物や反応熱が生産される事や、またその重合体が放出する核子磁束が金属原子を打ち抜いて核変換を起こせしめている事実や、あるいは重水素ガスそれ自体が磁場内部で圧縮融合し長鎖の核重合体を形成する事実など、この様な不可思議な核反応を既存の理論で説明する事は困難である。
これらの現象に対して、様々な科学者が様々な理論モデルを提唱しているが、いずれも部分的であり、今の科学知識では統括的な説得力に欠けているのが現状である。原子核は相変わらず謎多き未知の物体であり、我々の科学はまだその入口をほんの少し覗いただけに過ぎない。現在の核物理学がその現況を打破し大きく躍進する為には、もっと大胆で革新的な理論ベースが必要と思われる。そこで、低エネルギー核反応のみならず全ての核反応を説明出来得る全く新しい統一理論モデルを紹介しようと思う。この体系理論は今の量子力学や素粒子物理学や電磁気学の基礎理論とは全く異なるものであり、その理論基盤はニュートン力学以前のデカルト宇宙論(空間媒体の理論)に起源を発している。ここではその中から原子核理論のみを抜粋して説明しようと思う。
理論の説明に入る前に、原子核の基本的な成り立ちについて今一度良く考えてみたい。原子核は陽子と中性子の塊(かたまり)であるが、それらの粒子が何の規則性も無く、ただダンゴ状態で凝集しているとは考えられない。なぜなら放射能元素は皆、α崩壊という力学的に不可能なトンネル現象をいとも簡単に引き起こすからであって、原子核が核力によって異常なほど強固に凝集したものではなく、早い話がヘリウム単位で整然と崩壊してくるのであれば、それは元々ヘリウム単位で構成されており、我々の想像以上に柔らかい物ではないかという単純な推理が成り立つからである。
そもそもヘリウムとは二組の重水素ユニットが融合したものであって、宇宙の最初期に発生した万物の本源とも言える重水素ガスの存在を考えれば、原子核が基本的にHe単位(ヘリウム単位)もしくはD単位(デュートロン単位)から構成されていると推察するのは別に不自然な話ではない。人類の男女の数が均等な様に、あるいは原子の中の電子と反電子の数が均等な様に、陽子と中性子の数も均等であって、この世は対の法則が当てはまる整然とした世界なのではあるまいか。つまり、新しい発想法とは、原子核の陽子と中性子の存在比率が如何なる元素の場合も基本的にほぼ“1対1”であるという考え方である。
② 電荷の正体とは何か
我々は学校の授業で、ウラン(U238)は92個の陽子と146個の中性子から成り立つと教えられた。だがそれは本当の話なのだろうか。その数は陽子の電荷量に基づく単なる推定値に過ぎなく、実際に原子核を肉眼で見てその数を勘定した者は誰もいない。現在の科学では電荷の意味や定義すら、あるいは陽子や中性子の定義すら曖昧で不確定な状態であって、果たして元素の核子数をそんなに簡単に確定してしまって良いのだろうか。ウラン原子核の中に92個以外の陽子は存在しないのだろうか。もしウランが119個の陽子と119個の中性子から成り立つと仮定してその原子核力を計算すると、原子核は大変柔らかい物となり、α崩壊などはトンネル効果でも何でもなく簡単に起こり得る現象となるのである。我々の科学は20世紀のどこかで真理の道を踏み外していないだろうか。
ところで、陽子の持つ電荷量とは一体何の事だろうか。陽子は固有の磁荷量(中性子の磁荷量に相当する)の他に電荷量も備えている。だが中性子には電荷量が存在せず、陽子のそれに相応する磁荷量を持つだけである。陽子がその内軌道に存在する反電子を外界に放てば、それは中性子化して電荷を失ってしまう(β+崩壊)。その単体陽子は「疑似中性子」と呼ばれる陽子本来の原形に他ならなく、中性子と良く似てはいるが、スピンを異にする別種の粒子である。つまり、反電子を手放した単体陽子と中性子は正反対の磁荷を有する反粒子であって、対の粒子に他ならない。
従って、陽子の電荷とは陽子本来の持ち物ではなく、内在因子である反電子の所有物であって、反電子が無くなれば、陽子の電荷は失せて本来の磁荷量になるのである。我々が陽子と呼んでいるものは、正確に言えば陽子ではなく陽電荷陽子(actron)であって、反電子を所有していない原形体(プロトタイプ)こそ本来の陽子(proton)と言えるのである。承知の様に、この単体陽子は中性子と正反対の磁荷を持つ為に、「反中性子」と呼ばれている。
反電子を所有した陽子(actron)が存在するならば、当然電子を保有した陰電荷中性子(intron)も存在する。放射能元素の核分裂によって原子核の中から飛び出して来る高速中性子の多くは、素粒子物理学が言う所のいわゆる「反陽子」であって、電子を保有した有電荷中性子の事である。無論、この粒子は反電子を保有した通常の陽子と正反対の電荷を有している為に、「反陽子」と呼ばれている。単体陽子が「反中性子」で、有電荷中性子が「反陽子」だと言うなら、早い話が陽子と中性子は互いに反粒子だと認めているのも同じ事であって、その割にそういう認識が無いのは一体どういう訳なのだろうか。
③ 反粒子概念の誤り
陽子と中性子が反粒子ではないと頑(かたく)なに信じている理由は、反粒子同士ならば出会っただけでも“対消滅”するというディラックの理論を真に受けているからだと思われる。我々は皆、陰電子と陽電子が互いに対消滅して形態を失うものと信じているが、誰もが知るそんな常識的な見解でさえ必ずしも正しいものとは限らないのである。反粒子の消滅概念とは、[1 − 1= 0]としか考えられない現代数学の弊害であって、この世に相殺されて零(0)と成り対消滅するという現象は無く、そもそも(− 1)という存在自体が存在しない。
我々は(− 1)個の林檎を食べられないばかりか、(− 1)万円のお金を見た事も無ければ、またそれを使える筈も無いのである。数理を理解する為に便宜上の手段として導入されたマイナス概念が、その虚像の枠を超えて実像の如く見えるという錯覚はまま有り勝ちな話であって、ディラックは他の数学者と同様に、数理の罠に嵌(はま)って、“零の概念”を間違って認識してしまったに過ぎない。つまり、陽電子(+1)と陰電子(−1)が出会って零(0)に成る事は無く、“対消滅”する事は無いという話であって、(+1)と(−1)に別けられるのは電子の物性(電荷形質)に過ぎなく、元より電子の存在自体にプラス・マイナスが在る訳ではない。
酸(− 1)とアルカリ(+ 1)が遭遇しても、両者は化合して「塩」に成るだけであって、互いに消滅する訳ではない。それは酸性とアルカリ性が相殺(中和)されて、物性がどっち付かずの状態(零状態)になっただけの話に過ぎない。その証拠に、「塩」が溶解すると再び酸とアルカリに解離する事は承知の通りである。
それと同じ事はヘリウム原子核でも言える。一見、核スピンを持たないhelium原子核だが、良く観察すると、左回転するdeuteron単位(+1)と右回転するdeuteron単位(−1)に別れてスピンしている。両者が合体してヘリウム原子核を構成している間は確かにスピンは相殺されているが、そもそもスピン自体が零になった訳ではない。その証拠に、両者が分離して単体になると、それぞれの物性であるスピンが出現してくる。
つまり、 現実のこの世では [1 − 1 = 0] という数式は成り立たないのであり、本当に消滅する物など何一つ存在しない。数理で扱う場合の零(0)という概念は、何も無くなるという意味ではなく、相殺されて原点に戻ると解釈しなければならない。ディラックの理論では、男性(+ 1)と女性(− 1)が遭遇すると対消滅して(零になって)無くなってしまうという考え方である。反物質である男と女が合体しても一組の夫婦(0)が誕生するだけであって、それは別に消滅を意味するものではない。相殺されるものはそれぞれの物性であって、所帯を持つと互いの雄性(+1)や雌性(−1)が相殺され、独身時代と比べて比較的魅力が無くなる傾向は確かに否めない。だが、それすらも完全に無くなる訳ではなく、ただ中和されて隠れ潜んだだけの話である。ペアーを解消すれば、つまり夫婦が離婚すれば、それぞれが持つ形質(雄性や雌性)が再び強く現われてくる事は承知の通りである。
激しい反応力に富んだ酸素原子はあらゆる物を酸化してしまう過度な攻撃力を備えている事は承知の通りである。単体の酸素原子の中では生物はその肉体を維持する事すら難しい。そこで酸素原子は互いに反転して結合し、“酸素分子”を形成して、その激しい反応力を相殺して仮の零状態にしている。生物は酸素原子の空気の中では生きられないが、酸素分子の空気の中では生きられるのであって、酸素原子の相互合体(分子結合)の真意は、単体が備える激しい活性形質を抑制する為の手段に過ぎない。
DNAの二本鎖の構造を見て、なぜそれが二本鎖でなければならないのか、貴方は疑問に感じた事はないのだろうか? 一本鎖を合体させて両者の物性を相殺しなければ、ウイルス(一本鎖RNA)の如く無制限に増殖して、統制(バース・コントロール)が効かなくなってしまうからである。生物はDNAを対状態にして保管し、必要な時に必要な分だけ裸の一本鎖にしてタンパク合成情報を得ている。つまりDNAは零(0)状態に成っているのであり、それは勿論DNAが無いという意味ではない。酸素原子にしてもDNAにしても、なぜ互いに“対状態”を呈しているのか、自然の奥深い道理を認識する必要があるだろう。
この様に考えていくと、電子(男)と反電子(女)がγ線を放って互いに消滅するという反物質の既成概念は明らかに間違っており、電子と反電子は互いに頑強なクーパー対を形成し、無電荷の「π電子対(夫婦)」を形成したと考えなければならない。それは消滅したのではなく、検出不能な「無電荷粒子対」へと変貌したのであって、互いの電荷が相殺されただけの話に過ぎない。その証拠に、任意の空間にγ線を打ち込んでやれば、それを吸収したπ電子対が励起して電子と反電子に分かれて発生してくることは承知の通りである。γ線の放出は、両者が合体した際の振動が光波動を揺り起したに過ぎず、それは特別な事ではない。この宇宙空間には無量大数のπ電子が浮遊していると言って良いだろう。
π電子対と同じ事は陽子と中性子にも言える。陽子(actron)と陰電荷中性子(intron)は反粒子であって、これらが結合すると互いの電荷量が相殺されて無電荷粒子対を形成する。この無電荷粒子は互いの電荷量と磁荷量が相殺されている事は勿論、大きな原子核の内核(中心部)に「隠れ重陽子」として潜んでおり、原子核の総電荷量には現われない特徴を持っている。主にβ‾崩壊などの–核反応の主役を演じているのはこの無電荷粒子に他ならない。ちなみにU238 の無電荷粒子数は27組であり、原子核の奥底には27個の陽子(actron)と27個の陰電荷中性子(intron)が存在すると思われる。
人間が創作した軽薄な数理から「何かの自然原理」を読み取ろうとすれば逆に物事の道理を見失ってしまうのであり、それはcomputerを先に作って、computerから真実を教えて貰おうとする愚かな行為と何も変わるものではない。その昔、ピタゴラスを始めとする古代ギリシャの7人の賢人達(数学者)は皆“哲学者”だった。彼等は自然の道理に則して数理や数論を作り上げており、数理から道理を伺う様な本末転倒した考え方は誰も持ってはいなかった。そのギリシャ哲理が中世ルネッサンスで開花して、哲学者であるデカルトによって集大成されたが、“近代数学の始祖”と呼ばれるそのデカルト本人でも、「負の概念」は導入したものの、「負の解」の存在自体を認めていなかった。彼はあくまでも認識の都合上、便宜的な手段として「負の概念」を導入したに過ぎない。
しかし、デカルト以後の数学者は皆“哲学者”ではない。彼等は現実には存在しない「負の概念」をあたかも実在するかの様に操作して、鏡に投影される「虚像の数論」を組み立ててしまった。フェルマー、パスカル、ライプニッツ、ニュートン、オイラー、ガウスなど、俗に数学の天才と呼ばれる数学者達は全員「数理の魔術」に陥った当人であり、数理から道理を判断する輩(やから)に他ならない。道理とは自然が従う宇宙の法理であり、そして数理とは人間が創作した法理に過ぎない。
もし、ニュートンが道理を求める哲学者であったならば、つまり、数理的な発想をベースにするのではなく、物事の成り立ちから判断識別していく重厚な洞察眼を持っていたら、重力という片道通行の向心ベクトル(片道ベクトル)を物体引力(往復ベクトル)と勘違いする様な基本的なミスを犯さなかっただろうし、もし、ガウスが数学を学ぶ以前に哲学を学んでいたら、磁石のNSを勘違いする様な初歩的なミスは犯さなかっただろう。
相対性理論や波動方程式から一体何が分かったと言うのだろうか? 数理を先行させれば、逆に数理の罠に嵌まるのであって、そもそも物事の道理も分からないうら若い数学者が宇宙哲理を憶測するべきではない。現代物理学の多くの科学者が数学の魔術に陥っており、それを崇め信奉する余りに、自己の頭脳を使って考察し、判断する術を忘れていると言っても過言ではないだろう。この世には数理から読み取れる真実など何一つ存在しないのであって、真実を解明した後に、数理に要約して簡素化し、認識の役に立てるというのが数学本来の役割であり、所詮数学とは元々その程度の価値のものでしかない。
さて、新しい原子核理論の根幹となる考え方は、原子が三つではなく四つの基礎素粒子から成り立つというものである。それは二組の反粒子ペアーから構成されており、電子(electron)と反電子(positron)、そして陽子(proton)と中性子(neutron)という四つの基礎粒子の事である。その他の粒子(例えば反陽子や反中性子)は核子が電子や反電子の有無によって姿を変化させたものであり、独立した素粒子とは認められない。この様な考え方をベースにして理論モデルが出来上がっており、核分裂や核融合といった原子核反応について新しい角度から考察してみようと思う。
B 星の核反応についての理論モデル
① 水素爆弾は存在しない
太陽が核分裂で燃えているのか、それとも核融合で燃えているのか、科学論争が盛んに行われた時代があったが、ビキニ環礁で水爆が爆発して以来、その論争には終止符が打たれ、核融合の方に軍配が上がった事は承知の通りである。その論争を今更再燃させるつもりはないが、太陽で起こっている核反応とはコアという巨大な核物質の「核崩壊=核分裂」であって、太陽は核融合で燃えている訳ではないというのが新しい考え方である。
驚かれる方も多いと思うが、別に核融合自体を否定している訳ではない。正確に表現すれば、核融合反応によって完成したコアが崩壊する際にエネルギーが放出されるという考え方であり、核融合反応と核分裂反応は表裏一体の反応であって、その中でもエネルギーを放出するのは核分裂反応のみである。核融合反応とはエネルギーを生み出す反応ではなく、逆にエネルギーを「消費」する反応であって、外部の力によって星のコアが完成するまでの行程を核融合行程、その完成したコアが分解してエネルギーを放出する行程が核分裂行程に他ならない。物事の道理から言っても、物を作る反応行程はエネルギーを生み出さない。エネルギーを生み出すのは物を分解する反応であると相場は決まっている。
核融合反応がエネルギーを出す反応でないならば、当然、核融合爆弾(水爆)の存在も無い。それは何かの勘違いと言わなければならない。水素爆弾とは起爆剤である中身の原子爆弾が炸裂しているだけに過ぎなく、実際に核融合連鎖反応が起こっている訳ではない。承知の様に、原子爆弾は実験室で核分裂連鎖反応が確認された翌年に作られた爆弾である。だが、水素爆弾は実験室で核融合連鎖反応が確認される以前に突然爆弾の方が先に完成した疑惑付の爆弾である。その後50年が経過しても、核融合連鎖反応は実験的にただの一度も成功しておらず今日に到っている。理論推定値の数百分の一にも満たないその爆発力では、水爆は軍事的優位を保つ為の「軍部の真っ赤な嘘」と陰口を叩かれても仕方が無い。それは単なるプルトニウム爆弾をトリチウムの衣で包んだ中性子爆弾に過ぎなく、生命殺傷用の劣悪な原子爆弾に他ならない。この地球上に核融合爆弾など存在しない事を我々は認識しなければならないだろう。
② 間違った核融合概念
そもそも核融合理論とはヘリウム原子の質量欠損に端を発した理論であり、それはアインシュタインの「E=mc2の定理」に根ざしている。星の重力を物体引力と考えるか、それとも磁場の内部吸核力と考えるか、つまり重力とは地球という物体が所有する牽引力なのか、それとも頭の上から圧縮してくる磁場の力なのか、たったそれだけの事で重力場の質量概念は180度変化してしまう。もし重力が地球磁場圏から地球内核の中心点に対して入力してくる磁場の向心力ならば、物の体重は角運動量の程度によって変化し、スピンの形態次第で体重が軽減する事になるのである。ニュートン力学を超えようとしたアインシュタインだったが、重力が物体の質量引力であるという既成概念を打ち破れなかった彼は、結局ニュートンの“弟子”に過ぎなく、“師の器”を少しも超えていない。
2個の重水素単位に分かれて核スピンするヘリウム原子核は、外から覗くとスピンが相殺され、一見回転してない様に見えるが、実際はバラバラで核スピンする四つの陽子の総合体重よりもスピン量が多く、その分、磁場の重力に反発して体重が軽い。ヘリウム原子核は四つの核子が独自にスピンしている他に、重水素単位でもスピンしている。つまり、スピン量が多いのが体重差の原因である。だが、体重は変化しても物量が変化する訳ではない。見せ掛け上の体重差は生じても、それはエネルギーとは全く無関係な話であって、質量欠損によるエネルギー移動など有り得ない話である。その様な意味では、本当か嘘かも分からないいい加減な数学者の形容方程式に惑わされて無理やり生み出された詭弁理論、それがベーテとワイツゼッカーの核融合理論と言えよう。
③ 核崩壊で燃える太陽
核分裂で燃える太陽と言っても、ウランやプルトニウムの様な小さな元素の核分裂の意味ではない。星のコアそのものを一つの巨大原子核と考えれば、それが核分裂する際のエネルギー放出こそ星が燃える原動力に他ならない。コアが燃えて分解すれば、当然排気ガスが吐き出される。太陽の周囲に群がる膨大な量の水素とヘリウムについて、それを核融合の燃料と考えるのか、それとも核分裂の排泄物と考えるのか、その違いは余りにも大きく、その重大な選択肢を科学は見誤ってしまった。圧縮された重水素の凝集体であるコアが小さな単位に分解していくならば、星は当然、その体積を増していくだろうし、もしそれが核燃料だと言うならば、星は成長と共に縮小しなければ理屈に合わない。
100個の陽子を圧縮して核(コア)を造る時の消費エネルギー量と、そのコアが分裂崩壊して100個の陽子に戻る際の放出エネルギー量は全く一緒である。しかし、エネルギー量は同じでも、その数値にはプラス・マイナスの違いが存在する。太陽総質量からその全放出エネルギー量を核融合計算した数値と、核分裂計算した数値は全く一緒である。核分裂反応が存在するならば、その反対の核融合反応も存在するだろうと推察するのも結構だが、両方ともエネルギーを生み出す反応であると都合良く解釈してしまうのはどうかと思われる。重要な事は、一つに思える核反応が実は前期と後期に分かれていて、片方の数値にはマイナスを付けねばならない事であろう。
図1 (写真: 太陽の燃焼)
考えてみれば、太陽も惑星も、あるいは単なる岩石星も、重水素ガス(星間ガス)が凝集して出来た物体である事に変わりはない。最初期の宇宙に存在する唯一の物体は重水素ガスだけであって、それらは一体何の力によって星の中心核に集約されたのだろうか。それが星の爆風によって集まるものなら、果して星が誕生する以前に超新星爆発が起こるものだろうか。エントロピーが増大の一途しか辿らないこの膨張宇宙に於いて、何の外部力も無くして、星間ガスが独りで勝手に集約する事は有り得ないのである。
図 2 (写真: 銀河系とブラック・ホール)
ニュートンの様に星の重力を物体引力と考えてしまえば、星が誕生してから重力が発生する事になってしまう。であれば何も無い宇宙空間のある一点に巨大重力源を持つブラック・ホールの存在とは一体何なのだろうか。そこに物体が何も無くても、気流の角運動(渦運動)が存在すれば重力は発生するのであり、その圧縮力によって重水素ガスが集約され星が誕生してくるのである。つまり、渦運動とは重力発生機関に他ならなく、また重力とは地球や太陽を産んだ源の力であり、星が誕生する以前から気流が回転し、その中心点には重力が向心していたと考えなければならない。当然、星の中心核に存在する物体はコアであって、それは重力によって重水素ガスが整然と配列した長鎖の核子重合体(重列元素)であり、少なくとも鉄の様な単独元素ではない。コアはこの宇宙の全ての原子核の原形母体であって、コアが分裂崩壊して100種の元素が誕生してくる事は述べるまでもない。
④ 未完成な力学
現代科学の誤りの根本原因は“重力の勘違い”と言えるが、無論それだけが原因ではない。我々地球人はこの宇宙の運動全てを理解している訳ではない。過去の科学者達が創った基礎力学が未完成のままに放置されてきたのである。ニュートンは角運動を解析し、向心力の入芯までは理解したが、それから先の力の循環運動までは理解が及ばなかった。結局、それが重力概念の間違いを生み出す結果となってしまう。物質の角運動(一点を中心にした公転運動の事)とは「力の場」を形成する根幹の運動であって、そこには回転する磁場が形成されているのである。
例えば、地球の公転運動も、あるいは電子の公転運動も、あるいは大気や水面の渦運動でもその力の場は形成されている。ハリケーンやトルネードが上空に訪れると、なぜ海面が盛り上がり、物が吸い込まれるのだろうか。その理由を、それらの渦巻きの中が真空状態になるからだと説明するのは小学生の解答だと言わねばならない。我々科学者たる者は渦巻きの中を真空にせしめる力が一体どこから作用しているのか、それを考えなければならない。海面に発生した巨大渦巻きがその真上を飛ぶカモメを吸い込んでしまう現象に対して、我々は果たしてどんな説明を付けられるのだろうか。この様な角運動やそれが形成する力の場については後章で詳しく説明している。
ニュートンは磁石が鉄粉を引き付けるのを見て万有引力の存在を想定したが、果して磁石は鉄粉を引き付けているだろうか。その現象は磁石の磁界の求核力が鉄粉を中心点に押し付けている現象ではなかろうか。なぜなら電磁石の空芯コイルの中に物体は存在しておらず、何も無い空間であってもそこが磁界の中心点であれば鉄粉が集められるからである。であれば、物体の所有する質量が引力の源泉と考えるのは見当違いも甚だしい限りだと言わねばならない。その考え方であれば、地球と同じ質量の巨大宇宙船を造れば、人間はその質量引力によって宇宙船の上に立てる事になってしまう。たとえ直径が100mの岩石星でもそれが磁場を持つ物体ならば人間は立つ事が出来るのである。
承知の様に、磁石の磁性はその成分である鉄やコバルト原子の磁性に起因している。一個の鉄原子の磁性は複数のd-軌道電子の角運動からもたらされるものであって、電子公転がその公転半径を超える巨大磁界を形成している事実を我々は知らない訳ではない。しかし、そのメカニズムは全く明らかにされておらず、未知の状態である。月の公転運動が月の軌道磁界を形成し、その力の場に地球はすっぽりと覆われている事は勿論、その影響を受けながら地上の生物は育まれてきた。生物に月周期が深く関っている事実は述べるまでもないが、その影響は地球重力にまで及んでいるのである。なぜなら、月の向心加速度と地球の表面重力加速度は一致するからであって、その様な磁界のなせる不思議な技について、我々が無知である事を認識しなければならないだろう。
C 星の核崩壊メカニズム
① 空間媒体(気)の理論
かつて、デカルトは地球に大気が存在する様に、宇宙空間にも光の波動を媒介する極小の空間媒体(光エーテル)が存在し、その渦運動によって星が誕生し、そしてその回転力によって星の運行が行われていると考えた。それに対して、うら若きニュートンは理論根拠の無い神学的な迷信発想を嫌い、物体(星)が持つ万有引力(質量引力)によって星の運行が行われていると考えた。当然、その様な発想法に立てば、空間媒体の存在を否定し、また光を粒子にしなければならない。
もし、デカルト理論が本当に正しければ、太陽系の中から太陽を取り出しても、地球はその公転軌道を失わずにそのまま回転を続ける事になるのである。なぜなら、地球が公転しているのではなく、太陽系そのものが回転しているからであって、地球は空間媒体の巨大渦流に浮いている存在に過ぎないからである。この様に、両者の考え方は鏡の実像と虚像の如く“180度正反対”であって、そのどちらかが間違っている事は確かである。この統一理論モデルはニュートン力学を否定し、こうしたデカルト科学を理論的に体系化したものであって、その様な意味からも、“空間媒体(気)の理論”と自称している。本格的な説明に入る前に、ここでは先ずこの「気」について簡単に説明しようと思う。
計測不能なこの世の最小単位である「気(fozon)」とは、極小の単位磁場(点磁界)の意味であり、宇宙力(磁気=force)を生み出す所の母源的な物質の意味である。この宇宙は気の収縮と膨張を繰り返す反復宇宙であり、また気とは唯一無二の絶対的な存在であって、この宇宙には気しか存在しない。というより気こそ宇宙そのものと表現した方が早い。気はこの宇宙空間を埋め尽くす光媒体であるばかりか、万物を構成する本源的な物質である。更にこの気の運動から生まれる「力(force)」は万象を奏でる当体であり、物の形を維持する全ての運動を担うものと言えよう。具体的に言えば、陽子のコア(体)を構成するものは気の粒子だが、陽子の形を維持してその一切の生命活動を担うものは陽子の磁場に他ならなく、それは気の渦運動が生み出す「フォース」によって支えられている。
この様な空間媒体の理論はニュートンが否定したにも係らず、科学者達の間では19世紀後半まで根強く信じられてきた。なぜなら、宇宙空間を皆無の真空にしてしまえば、無から有が誕生する事になってしまうからである。空から雨粒が誕生してくる様に、そこに何かが存在するから物質が生じてくる。そこに何も存在しなければ何事も起こらないし、また何物も生まれてこない。それが物事の道理だと考えられてきたからである。しかし、こんな常識的な宇宙観でも、アインシュタインの出現によって打ち消され、再び我々の科学は350年前のニュートンの時代へと舞い戻ってしまう。その結果、科学は何も分からない盲目的な唯物科学へと変貌してしまったと言っても構わないだろう。
しかし、ようやく最近になって今の科学を根本から見直そうとする傾向が高まり、空間媒体を仮定した科学理論がチラホラと出現し始めたが、過去の全科学者の理論を一挙に打破出来る様な統一理論の完成は未だ出来ていないのが実情である。本誌に紹介したこの統一理論がその最初のものと言えるかもしれない。さて、話を星の核反応に戻そう。
② コアの形成と燃焼
星の核反応とは、重力の下で圧縮重合した重列元素(コア)が、その重力の減退に伴って徐々に核崩壊を進行させていく事である。超密度に圧縮されたコアはその表層部から中心部に向かって核崩壊を始め、その時の崩壊熱が星の燃焼エネルギーとなっている。大きなコアを有するものは表層の地殻を越えて炎が噴出し恒星となるが、小さなコアを有するものは早い段階で表層が冷えて内部で炭火の様に燃え続ける惑星となる。星の一生はコアの生涯であり、その運命はコアの大小によって定まると言って良いかもしれない。無論、地球は月よりも小さなコアから出発して現在の大きさに膨張してきた。そして地球は今も尚膨張していると言ったら貴方は驚くだろうか。星は皆コアの核崩壊によって100種の元素を生産しながら、成長とともに段々とその体積を増していくのである。
星間ガスである重水素原子が重力の圧縮力の下で、整然と配列した核子の重合体を星の中心核に創造していく事が物質宇宙の始まりである。ここではその重合体を重列元素(matrix element)と称しているが、その正体とは中性子と陽子が串ダンゴ状に磁極結合した重水素ユニットが長く連鎖したものである(deuteron chain)。その長鎖の棒状重列元素はそれ自体が高速でスピンする1本の棒磁石を呈しており、両端の磁極の片方(N極)からは重列元素を貫通する核子の中心磁束が吹き出している。無論、それが地磁気の正体に他ならなく、地球内核の中心部を貫く磁気ダイポールに沿って無数のデュートロン・チェーンが配列して、巨大なダイナモ核子(コア)を形成している。
図 3 (重列元素想像図)
地球磁場圏を形成する外磁場は気の渦流から生じる渦磁場であり、重力を生み出す本源的な磁界である。その奥行きは広く、高度半径は約2千万Kmにも達する超大なものである。一方、重列元素(コア)が生み出す物質磁界は磁北から地磁気を吹き出し、高度半径が約10万Kmに達する内部磁界を形成しており、地磁気は磁界を形成しながら磁南に吸収されて大空を循環している。極地方にオーロラが観測される理由は、磁極から吹き出す(もしくは戻る)コアの中心磁束が周辺の浮遊物体を吹き飛ばして振動発光させるのが原因である。いずれにしても、地球磁場圏には性質が異なる2種類の磁界が存在し、地球は分厚い磁気の庇護膜でガードされた状態と言える。
デュートロン・チェーンの集合体である重列元素の最大の特徴は、それが外殻電子を持たない原子核だけの重合体であり、物質に分化する以前の原始的な超物体であるという事である。外殻電子はその収納母体である中性子からまだ分離しておらず、電子を備えた中性子は陰電荷中性子(反陽子=intron)として重水素ユニットに組み込まれ、陽子と磁極結合している。当然、陽子は反電子を保有し、また陰電荷中性子は電子を保有している為に、両者は無電荷粒子として重水素ユニットを形成している。
従って、デュートロン・チェーンも無電荷であれば、また重列元素全体も無電荷を呈しており、コアの外側から電子の存在や陽子の存在を確認する事は出来ない。重列元素を一見すると、それは全て中性子から構成されている様に見えるのが特徴である。宇宙に存在する中性子星(パルサー)とは、巨星の外輪が崩壊してコア内核の芯が残骸物として残ったものであり、それは中性子の固まりではなく重列元素そのものであって、無電荷粒子の集団と言えよう。
③ 重列元素と100種の元素
重列元素の無電荷状態は強い重力下における高密度の気の存在によるものである。空間媒体である気(fozon)の圧力(fozonial pressure)が充分に高いと、全ての粒子は基底状態となり個々の運動を抑制して休眠状態となる。原子核の外殻軌道を周回する電子は本来の帰属先(中性子の内軌道)に戻って、原子は原子核だけの存在となる。その理由は、重列元素という組織の中に於いては、個々の粒子は個別の生命活動をする必要が全く無いからである。つまり食料となる気の粒を集める努力も、あるいは自己の回転(スピン)を維持するのに光エネルギーを吸収する努力も必要が無いのがその理由である。それは人間が個人として単独で生きるのか、それとも会社や軍隊という団体組織に従って生きるのかという問題と同じであり、生計を得る為の企て事(ビジネス)を考える必要がない後者の方が遥かに楽チンなのである。団体組織に入った人間はもはやアンテナ(外殻電子)を張る必要がなく、ただ命令に従っていれば、それで生きていける事は述べるまでもない。
その反対に、重列元素の破片が気密度の薄い場所に出ると、つまり組織の人間が単独で外世界に出ると、その瞬間から過酷な現実に直面する事になり、彼はその日から生きる為の努力をしなければならない。本体から分離した破片が直面する問題は、食料の安定獲得と運動エネルギーの獲得である。しかし、原子核の核磁場の容量では大量の気や光を集める事は難しい。そこで、重水素ユニットの陰電荷中性子(intron)は電子を外界へ放って軌道運動させ、自己の磁場容量の拡大を図るのである。電子の角運動によって形成される軌道磁界は原子核のそれの10万倍にも達し、その巨大磁界で効率良く気と光を集めている。重列元素から分離したその破片は電子を外界へ放って外殻電子を備えた電子系物質(元素の事)として独立した生命を維持していかねばならない。無論、大きな元素の原子核はコア同様に外核と内核に分かれており、電子を放つのは表層の外核中性子のみであって、内核の中性子は電子を保有した状態であり、無電荷粒子として原形のまま存在している。
さて、重列元素の核崩壊はマントルを生み出し、その内部で100種の元素が育まれる。元素とはいわゆる重列元素から分離した破片であり、元々一本鎖のdeuteron chainが折れ曲がって二本鎖のhelium chainとなり、それらが零磁場の核子集合体として一塊の状態にくるまったものである。この巨大な核子重合体(nucleon cluster)は超ウラン母源元素(trans-uranic pre-element)と呼ばれる元素の前正体であり、これらが核分裂して更に小さな安定同位体へと遷移し、100種の元素が誕生してくる。無論、これらの元素の最初は核子の集団に過ぎなく、核子は自己の内在電子を外界へ放って“電子系物質(electro-systematic substance)”へと進化し、一個の生命単位としての存在を勝ち得る。
④ 細胞と星は親子か
ところで、重列元素から分離したdeuteron chainと、それが二つ折りになったhelium chainは、その形状が細胞の核物質である遺伝子(一本鎖RNAや二本鎖DNA)と大変良く似ている。星の核物質も細胞の核物質も、その中心部には長鎖の高分子重合体(polymer chain)を所有し、その構造も瓜二つである。例えば、星は液体のマントル流動体の中に固体の中心核を持ち、その上には庇護膜の地殻が存在し、その全体が磁場圏の皮膜で包まれている。それと全く同じ様に、細胞も液体の原形質流動体の中に固体の中心核を持ち、その上には庇護膜の細胞膜が存在し、その全体が生体磁場(アミノ磁場)の皮膜で覆われている。この様に考えれば、星と細胞の間に構造上の大きな違いはない。細胞とは地球が自己の形態を真似て作った「地球の子供」ではなかろうか。
だが、似ているのは何も形状や構造ばかりではない。特に二本鎖のhelium chainとDNAは大変良く似ており、その鎖の構成単位は四分子体の連鎖結合(helium単位とAGCT塩基)であって、その四分子体も結局は異なる2種の単位(陽子と中性子;プリンとピリミジン)から成り立っている。無論、これらの2種の単位の存在比は互いに“1対1”であって、「対の法則」を超えるものではない。一体、自然は何を模倣して生物の遺伝子を創造したのだろうか。宇宙の奥深き神秘を感じざるを得ない。
さて、元素が辿る運命の潮流は、山が崩壊して岩石となり、その岩石が崩壊して砂粒へと姿を変えていく物質の変遷と一緒の方向である。大きな元素は皆小さな元素へと向かって一方通行の崩壊行程を歩んでいる。崩壊の最終段階にはヘリウム単位となり、更に細かく分裂して元の原形である水素原子へと戻るのである。水素から誕生した元素は結局もとの水素へ帰納するのであって、それは平地から誕生した山が風解して結局もとの平地へ戻るのと同じ理屈である。100種の元素とは核融合によって作られたものではなく、あらかじめ創られた巨大元素が核崩壊する途上に発生するものであって、長い崩壊行程を辿る途上の[仮の安定体]というのがその本当の姿に他ならない。
その様な意味では、鉄に中性子が突き刺さって大きな元素が創造されたと考える思想は中世の錬金術師の遺伝病だと言えよう。元素とは小さな単位が大きな単位へと成長してきたものではない。銅とバリウムを合体させた所で金が出来る筈もなく、その様な核融合的発想は真理の方向とは正反対であって、間違った考え方と言わざるを得ない。
それと全く同じ事はDNAでも言える。果して遺伝子とはDNA合成ポリメラーゼが創造してきた生物の獲得形質なのだろうか。つまり、生物は自らのDNAを進化の段階に応じて増産してきたのだろうか。その様な核融合的な発想で、遥か太古の昔に起こった「細胞の発生」を正しく洞察出来るものかどうか疑問である。人間のDNAを持つ“ヒト受精卵”が母親の子宮の中で、単細胞生物から発生して魚類や爬虫類の時代を通過し霊長類人科まで進化する行程を考えれば、優れた遺伝子を獲得したから進化したのではなく、DNAは最初から変わらない原形を保った状態ではないかと想像出来る。
核分裂的な発想をすれば、遺伝子とは合成されたものではなく、分解してきたものと考えなければならない。原始海洋の中で最初に創造された「巨大核酸(RNA-polymerの集合体)」がバラバラに分解して、長鎖や短鎖の多様な長さの核酸が生じ、それらを中心核にして細胞膜を作り、内環境を整えて細胞が誕生してきたのではあるまいか。
長鎖のDNAを中心核にして発生してきた者は多種類のタンパク合成が可能であり、高等動物までの進化の道程に対応出来たが、一方、短鎖のDNAを中心核にして誕生してきた細胞は進化の行程から置き去りにされ、そのまま原始的な形態に甘んじたのではなかろうか。つまり、進化の能力は最初に与わった遺伝子の“長短”で決定されていたと考えねばならず、それは星のコアの“大小”で定まる星の進化と何も変わるものではない。星のコアも細胞のコアも同義であって、大きな物が崩壊して多様な生命単位(生物種や100種元素)が創造されたと考えるのが物事の道理であり自然な考え方と言えよう。
星のコアについて、科学が鉄だと主張する訳には二つの理由がある。その一つは今の核融合理論では鉄以上の元素が理論上作れないという理由である。もう一つは星の磁性を考えた場合、金属元素の中で最も存在量の多い強磁性体元素である鉄を中心核に置かなければ、地磁気の存在を説明出来ないからである。では、明らかに星の残骸物(コアの芯)と思われる中性子星の存在は一体どう説明すれば良いのだろうか。それが星の芯ならば、中性子ではなく鉄の固まりでなければならない。承知の様に、宇宙空間に鉄だけの固まりが発見された事例は一度もない。
⑤ コアの崩壊メカニズム
コアの崩壊を制御しているのは重力である。重力はコアを生み出すばかりではなく、その崩壊の促進と抑制をもコントロールしている。重力を例えれば、それはダムの防壁に相当するものであって、貯水した水量(重列元素)の調整を司っている。もし、ダムの防壁が決壊すればプールした莫大なエネルギーを一挙に放出する事になってしまう。重力が急激に衰えると、重列元素を圧縮する圧力が失われて、それは制御を失った原子炉の如く想像を絶する大爆発を引き起こしてしまう(超新星爆発)。
星の渦磁場(vortical system)はその角運動に伴って「位相運動」1) と呼ばれる特殊な運動を行っている。磁場の位相運動はこの宇宙の中でも最も理解が難しい複雑な運動だが、その一連の運動の一つに「潮汐運動」がある。潮汐も位相運動の一つだが、自転周期に伴い磁場全体がまるで呼吸運動の様に定期的に膨張と収縮を繰り返す運動であり、地球の場合は約6時間周期で、1日当たり4回の磁場の膨張と収縮が行われている。無論、ニュートンの月の引力仮説は間違っていると言わねばならない。
磁場の収縮が始まると、重力フォースが増大して重列元素の核崩壊は減退する。当然、この時重力の弱い赤道付近に偏在する海水が圧力を受けて離散し、各地に満潮を引き起こすばかりか、地殻プレートやマントルも同時に圧縮作用を受けており、それらの運動も抑制される。しかし、磁場の膨張が始まると、重力が減退し、重列元素の核崩壊が促進される。同時に地表の表面圧力も低下する為に、海水は重力が最も弱い赤道付近に流れ込み干潮現象が起こる。当然、抑圧された地殻プレート運動やマントル対流が開放されるので、地震や火山運動などの地殻変動も活発になるのである。子供の出産も火山噴火も、あるいは一連の群発地震も主にこの干潮時期に起こっている事は述べるまでもない。
この様な渦磁場の位相運動(phasic movement)のお蔭でコアの核崩壊は制御され、数十億年という長いスパンの星の核反応が維持されている。重要な事は、我々の地球科学はこの様な磁場の運動が存在する事実を知らないばかりか、そこに磁界が存在する事も、いやそこにフォゾン気流が存在する事すら知らない事であろう。地球の赤道上空を取り巻くバン・アレン帯や、土星や木星の赤道上空を取り巻く“環(かん)”の姿を見て、それが「渦のフレーム」であると認識するのはそんなに難しい話なのだろうか。あるいは、ブラック・ホールが単なる渦の中心点に過ぎない事を、それが銀河系やハリケーンの中心点と全く同じ物である事になぜ気が付かないのだろうか。結局、空間媒体の存在を否定した結果がこの様な劣化した「唯物科学」2) を創り上げてしまったと言って良いだろう。

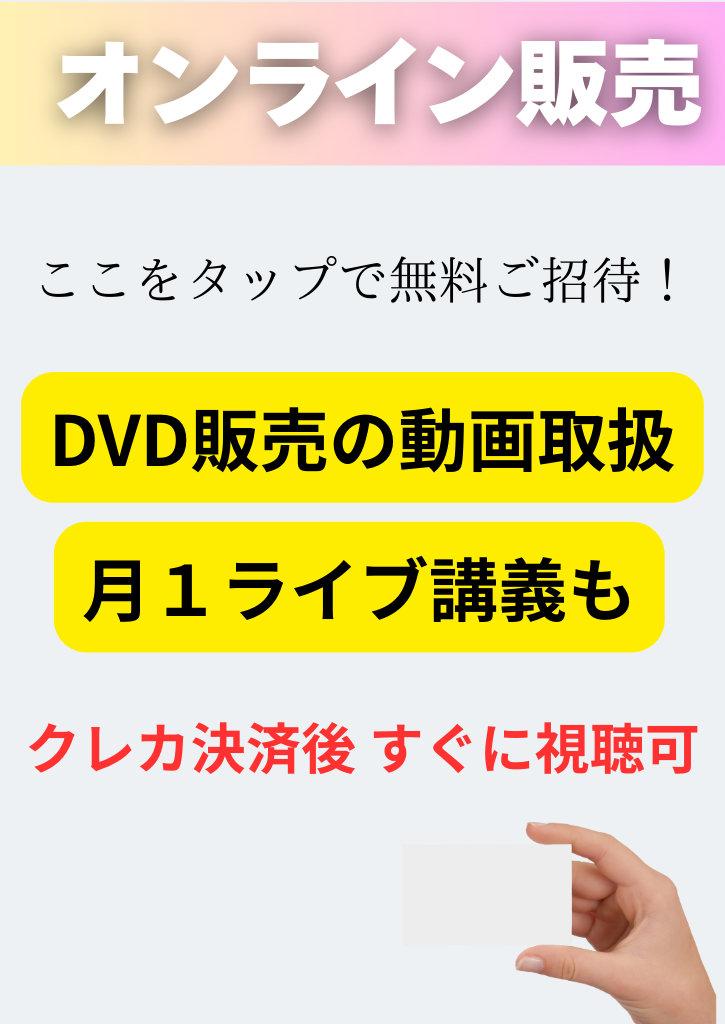





Comments are closed