〈原子核反応の統一理論モデル 2〉
原子核反応の統一理論モデル 2
D 低温核融合とDD反応
① 核反応の定義
核反応と言ってもその定義範囲は広い。放射能元素の様な自発的な核反応(α-崩壊やβ-崩壊や自発性核分裂など)も有れば、また光や中性子線や重イオンビーム照射によって人工的に引き起こされる核反応もある。核融合や核分裂だけが核反応ではなく、またハドロンやレプトンやメソンの様な極超微粒子の反応も核反応の一種と言える。一般に、原子核に対して何かの物理作用を加えると、原子核はその刺激に対して一連の反応を返してくる。科学界ではその一連の反応を核反応と定義し、原子核の構造や機能といった謎の解明を、その“返答的な反応(responsive reactions)”から逆に推察してきた。
しかし、原子核に外から人工的に刺激を与えてその反応から真実を解析しようという試みは如何なものだろうか。それなら大脳に電気刺激を加えて意識(心)のメカニズムを解明しようする手法と何も変わるものではなく、その様な方法では何年かけて研究した所できっと何の埒(らち)も開かないだろう。なぜなら、我々は人間の意識(心)が大脳の中に存在するという固定観念に取り憑かれているからであり、大脳とは我(心=外部意識体)と肉体を結ぶ単なる通信器官かもしれないからである。もし、大脳の中に記憶も意識も存在していないならば、そんな研究には何の意味も価値も無い。
そもそも、陽子が地球の様な殻を持った“一個の固体状の物質”であるという固定観念は如何なものだろうか。確かに目に見える地球は一つのパチンコ玉状の物質と言えるが、だが地球の本当の実体とは我々が想像するよりも遥かに大きなものである。実際、地球磁場圏は直径が4000万Kmに及ぶ巨大な球体磁界を呈しており、その磁界の壁を超えて他の惑星(金星や火星)が地球内部に侵入する事は出来ない。なぜなら、軌道を外れた火星が地球の至近距離に近づいても、互いの磁気反撥によって退け合ってしまうからである。それは陽子と陽子が互いに反撥して退け合う事と何も変わるものではない。
地球の本当の姿とは、銀河系(galactic vortical system)や太陽系(solar vortical system)と同じく「渦系:vortical system」を呈する回転磁界(渦磁場:vortical magnetic field)であって、目に見える固体の地球とは「回転系」の中心物体(center matter)、つまり一個の「コア:core」に過ぎないと言えるのである。
地球が銀河系や太陽系と同じく「惑星系:planetary vortical system」を呈しているならば、一個の陽子や中性子だって「核子系:nucleonic vortical system」を呈しているかもしれないと考えるのが自然である。我々が陽子だと思い込んでいる物は、実は一個の「陽子系:protonic vortical system」を呈するものであって、陽子の磁場圏なのかもしれないのである。陽子系内部の中心点には一個の中心物体(コア=気の凝集体)が存在すると考えられ、外部から強烈な衝撃を受けた場合は、そのコア自体が“重粒子(baryon:バリオン)”として系外へ飛び出すのではないかと考えられる。それは地球磁場圏に猛烈な衝撃を与えると、そのコア自体(地球本体)が外界へ飛び出してしまう事と何も変わるものではない。
もし、この仮定が真実であれば、「地球系」がその内軌道に子星(月=衛星)を抱いている様に、「陽子系」の内軌道にも子星(陽電子の事)が存在する筈であって、陽子が陽電子を放って中性子化する事実を考えれば、陽子の実体とは固体状の一物体ではなく、渦磁場を囲った“回転系物質(渦系物質:vortical systematic substance)”である事が容易に想像出来るのである。勿論、この仮説を用いれば、旧来の科学では説明が不能だった“陽子スピン”や“磁気モーメント”に対しても理屈の通った説明が可能となる。我々は陽子や地球がなぜ回転(spin)しているのか、その理由を知らないのである。
その様な意味では、陽子や電子の実体把握を道理に従って見定めようともせず、つまり、洞察力を使用せずに、ただ“返答的な反応”だけで数理的(機械的)に解釈し掌握してしまえば、まるで一個のパチンコ玉である陽子の腹の中から陽電子が飛び出してくる様な「とんでもない勘違い」を犯してしまう事になる。つまり、素粒子の持つ“力の場:force field”を先に解明しない限り、真理に到る正道を切り開く事は絶対に不可能であって、それは「素粒子反応」や「原子核反応」を語る以前の問題と言えるかもしれない。
この世に実在するものは唯一「気の粒」のみであって、基礎素粒子とは気の渦運動によって生じる“力の場(渦磁場)”が構築する“仮の姿”に過ぎない。その力の場が振動して光波動を生み出し、それ自体が表面磁荷量と磁極を備えた電磁ボールの如き球体磁界であって、それが素粒子の真実の素顔に他ならない。つまり、素粒子とは我々が想像してきた様なパチンコ玉状の粒子とは全く異なるものである。この様な新しい素粒子概念については後章で詳しく述べているので、ぜひ参考にされたい。
当然、この新しい物質概念から導かれる核反応の解釈が従来の解釈と大幅に異なる事は致し方もなく、我々の“場の科学(field science)”と旧来の“物質科学(material science)”の間には大きな隔たりが存在する。“場”とは“力の場(磁場)”の意味であり、この世の万物が固有の磁場を備えた「磁場単位(生命単位)」から構成されており、また、この世の万象がその“場と場”の係わり合いで成り立っているというのが我々の理論の基本コンセプトに他ならない。無論、この新概念の下で全ての核反応を説明出来なければ統一理論とは呼ぶ事は出来なく、我々には既にマクロの宇宙運動からミクロの粒子運動に到るまで説明出来る用意がある事は承知の通りである。
現在、我々はこの統一理論に基づき、重水素ガスを直接使用した様々な実験に取り組んでおり、未発表ながら科学界を驚かせる様ないくつかの実験に実際に成功している。我々は試行錯誤を繰り返す様な偶発的な実験を試みているのではなく、既に完成している理論に基づいて明確な意図の下に創作的な実験を行っており、科学解明の為の基礎実験には取り組んでいない。なぜなら、科学解明は既に終了しており、その必要が無いからである。その様な意味では、この紙面上に書かれている事柄が実験的な裏づけを得たものであって、この理論が単なる机上の空論ではない事を知って頂きたいと思う。
② 熱核融合の苦悩
核反応の一つに重水素(D単位)と重水素(D単位)が核融合を起こしてヘリウム(He単位)が出来上がるという「DD反応」が在る事は承知の通りである。太陽の中で行われているこの一般的な核反応を人工的に引き起こそうというのが現在盛んに研究されている“核融合実験”である。無論、その目的はDD反応が放出すると見積もられる“核エネルギー”を取り出す為である。
既に記述した様に、従来の核融合理論は誤って認識されており、DD反応でエネルギーが生産される訳ではない。常温でDD反応を引き起こす為には、DD反応が放出すると見積もられるエネルギー量と同等以上の付加エネルギーが必要である。しかし、付加エネルギーといっても、一体どんなエネルギーを与えればヘリウムが出来上がるのだろうか。
D2ガスを熱していくと分子運動が盛んになり、D2分子は活性して激しく飛び回る。それを更に加熱すると、分子状態が解けて原子状態となり、更に熱を加えると、電離したそれは高温のプラズマ状態となるだろう。だが、熱エネルギーをどんなに加えた所で、粒子は益々個々の運動能力を増加させるだけで、おとなしく結合してくれるものではない。強固な磁場を作って、その空間に高温プラズマを閉じ込めようとしても、勢い余ったD+イオンを完全に封じ込める事は大変難しい。現在の熱核融合はそんな苦労をしている。
1億度を超える超高温下で、軌道電子を無理やり剥ぎ取って裸の原子核同士をぶつけ合っているのだから、瞬間的にはごく一部分が結合してヘリウム原子核が形成されるかもしれない。だが、それも瞬時の出来事であって、発生したヘリウムは次の瞬間には解離して重水素に戻ってしまう。そもそもヘリウムも解離してしまう様な極超高温下でどうしてDD核融合反応が起こるだろうか。エネルギーを出す、出さないは別問題として、DD反応を起こしたいならば反対に極超低温にしなければならない。
所で、熱線(赤外線以下の波長)は分子サイズの物質にとってはこの上もない増幅エネルギーと言えるが、原子サイズの物質には振動エネルギーとはならない。重陽子(重水素)サイズの粒子を最も励起させる光の波長はX線であり、威力のある硬X線を吸収したそれはスピンが吸核的に増幅されて、外殻電子を手放しプラズマ状態になる事は勿論、強い中心磁束を外界に放出して他の中性子を引き付けて一時的にトリチウムやヘリウムを作り出すだろう。しかし、猛烈に励起した陽子の電荷反撥は激しく、それ以上の核子重合体を生産する事は不可能であって、しかも加えたエネルギー以上にエネルギーを生み出す訳ではない。結局、熱核融合やこうしたX線核融合を成功させる事は至難の技であって、たとえ成功させた所で、エネルギーを生産しないならば何の意味も価値も無い。
式(1): ( D + D = He + 76.0 KeV + γ線)
式(2): ( He = D + D + 76.0 KeV + γ線)
(1)式と(2)式を見て、貴方は何か疑問を感じないだろうか。DD反応の放出エネルギーはHeの解離エネルギーと同じ値なのが不思議である。2個の重水素原子核が融合してヘリウム原子核が誕生する際にエネルギーを放出し、その誕生したばかりのヘリウム原子核が2個の重水素原子核に解離する際にも同じだけのエネルギーが放出されるという矛盾した考え方は本当に正しいのだろうか。(1)式はプラス・マイナスの符号を間違えており、それを正しく表現するならば、(1)式を(3)式の様に訂正しなければならない。
式(3):( D + D = He -76.0 KeV + γ線)
or ( D + D + 76.0 KeV = He + γ線)
無論、この反応に於けるγ線の放出は核子の振動から発生するもので、陽子と中性子が衝突合体する際の衝撃が光波動として放射されるものであって、エネルギー反応とは直接関係がない。だが、(1)式を改正して本来の形式に戻した所で、もともと(1)式も(2)式も現代科学が想定した浅はかな数式に過ぎなく、これらの数式には本質的な意味は何もない。それは一体なぜなのか、その理由をこれから語ろう。
③ 核エネルギーとは一体何か?
そもそもエネルギーとは一体何だろか? ウラニウム原子核が核分裂を起こすと、各種の電磁波線や各種の粒子線の放射以外に、爆薬の炸裂と良く似た特別の威力を持った破壊エネルギーが吹き出してくる。それは核力(原子核の凝集エネルギー)の放出なのだろうか? それとも単なる陽子と中性子の結合エネルギーの放出なのだろうか? いや、その様な類(たぐい)のものではあるまい。エネルギーとは原子核や原子、あるいは分子の磁場中に高密度に圧縮されプールされた“気の圧力(fozonial pressure)”の事であり、それが突然開放されて爆発的なエネルギーを生み出すと考えなければならない。我々はその気の放出エネルギーに数値を付けて計測する事は出来ないのである。
高速中性子を吸収したウラン原子が核分裂を起こしても、総勢235個の核子がバラバラに飛び散る訳ではない。それは大きく二つに分裂して、数個から数十の余剰核子が飛び出すだけの話に過ぎない。仮に、その放出エネルギーを核子の結合エネルギーの放出であると見積もっても計算が一致する筈もなく、核エネルギーとは我々の想像を遥かに上回る規模のものである事は承知の通りである。では、原子核が二つに割れただけで、どうしてそんな巨大な爆発エネルギーが生産されるのだろうか?
天然元素の中で一番大きなウラン原子は92個にも及ぶ大量の外殻電子を保有し、その電子の角運動が生み出す複数の「電子の軌道磁界」によって、膨大な気を磁場の中心部(原子核)にプールしている。高速中性子によって原子核が破壊されると、高圧の気流が軌道磁界を吹き飛ばして噴出する事は勿論、その衝撃が核子や電子を振動させ、あるいは周囲の空間を直接揺さぶって一連の振動波を生み出すのである。それは基本的に花火やダイナマイトの爆発と同じものであり、物質の磁場内部に蓄積した“気”を一度に吐き出させる原理と何も変わるものではない。
つまり、核分裂エネルギーを「原子核を纏めている個々の核子の凝集力の放出」だと想定した計算式では本当のエネルギーを語る事など出来ないのであって、それは計算式を立てる以前の問題だと言わねばならない。そもそも陽子と中性子が結合する部分力は原子核を構成する「D-unit」や「He-unit」を結び付ける力であり、原子核そのものを凝集する全体的な力とは無関係なものである。
もともと原子核はヘリウム単位から構成されており、それ自体は簡単に分割してしまう様な軟弱な構造のものに過ぎない。それを一塊に纏めている力は外部重力であって、軌道電子磁界の内部吸核力が原子核重力として作用している。それは地球という原子核と、その形状を外から維持している磁場の内部吸核力(地球重力)という“構図”と何も変わるものではない。早い話が、原子核引力によって軌道電子を引き付けているというニュートン力学を基盤にした発想であるから、エネルギーの正体を見誤ってしまうのである。
結局、エネルギーの具体的な正体が分からないから、陽子と中性子の結合エネルギーこそ核エネルギーの源泉であると詭弁化したのであって、その様な数学者のいい加減な発想から生まれた核エネルギー方程式を疑いもせずそのまま鵜呑みにしている科学者の方がどうかしていると言わなければならない。そもそも核子を結び付けているのは電磁気的な力であって、それは力線のなせる技であり、エネルギーとは根本的に違うものであろう。
アインシュタインは物体の質量自体をエネルギーと見積ったが、これもまたおかしな考え方であり、そんなドンブリ勘定ではエネルギーの本当の正体を具体的に認識する事は難しい。しかも、「E = mc2の定理」という根拠もヘッタクレも無い架空の質量方程式をデッチ上げるとは“ふざけている”と言わざるを得ない。これは俗に言う数学者の形容式と呼ばれるもので、原子核に潜在するエネルギーが“これぐらい凄い”ものであるという事を数式で表現したものに過ぎなく、その方程式自体に特別な意味がある訳ではない。フェルマーの定理、ニュートンの重力方程式、オイラーの公式など、数学者は自己の象徴とも言える何かの公式を世に残したがる。それを真正直に学んだ後世の科学者達が地球科学を“盲目のカオスの海”へと誘導してしまうのである。
核分裂とは早い話が核爆発の事に他ならなく、原子核の中に閉じ込められた高圧の気の爆発的拡散であって、それに付随して粒子線の放出や一連の振動波(光)が熱線として放出されているに過ぎない。従って、(1)式も(2)式もピント外れの方程式に過ぎず、その様な数値を想定する事自体が無意味な事であって、ましてやその数値を基準にして原子核反応を考察しようと試みるのは言語道断と言えよう。核融合概念が狂っているばかりか、核分裂概念すら狂っており、エネルギー概念そのものを根底から見直す必要があるだろう。
裸のヘリウム原子核(α粒子の意)とヘリウム原子(2個の外殻軌道電子を保有している)の違いを語るまでもないが、厳密に言えば両者の違いは外殻電子の有無だけではない。電子の軌道磁界を持つヘリウム原子はその分大量の潜在エネルギー(気)を保有している。それは重水素原子核(Deuteron)と重水素原子(Deuterium)の違いと全く一緒であり、原子核がその核磁場の中に保有するエネルギー量と比較すれば、原子のエネルギー保有量は規模も密度も遥かに大きい。重要な事は、原子核や原子が一度エネルギーを放出すると、再充填されるまでに時間が掛かるという認識である。
具体的に言えば、ヘリウム原子核が解離して二つのDeuteron-単位に分割された場合、ヘリウム原子核の核磁場が保有していたエネルギーは当然放出される。だが反対に二つのDeuteronが融合してヘリウム原子核が形成される場合は、そのヘリウム原子核は解離する以前のヘリウム原子核とは同じものではない。誕生したばかりのヘリウム原子核にはエネルギーが充填されておらず、核磁場が気を吸い込み集約していない。つまり、これは核融合の際にエネルギーは放出されないという意味なのである。
では、低温核融合実験などで実際に計測されている過剰熱や過剰電流等のエネルギー放出を一体どの様に説明すれば良いのだろうか。別にそれは難しい話ではない。そもそも、DD反応で放出されるエネルギーなどこの世には存在しない。熱線とは光であり、また電流とは電気力線(磁束線)の事であって、それらはエネルギーとは別種な振動波や磁力線の意味に他ならなく、磁場の崩壊によって放出される気のエネルギーとゴチャ混ぜにして考える事は許されない。電子や陽子などの基礎素粒子はそれ自体が一個の単位磁界であって、それらは振動しただけでも光を生み出し、また直列に並んだだけでも電流を生み出す性質を備えている。つまり、それらのエネルギーは磁界のなせる技であって、磁界が崩壊する際のエネルギーとは根本的に異なるものなのである。
「光」、「力」、「エネルギー」といった、物の基礎的な理解が不完全だからその様な曖昧な定義が生まれてくるのであり、“光とは何か”、“磁界とは何か”、“粒子とは何か”、“力とは何か”、そして“気とは何か”、その底辺を固めない限り、核反応を語る事など到底出来ない。現代科学は言葉で説明出来ないから数理を用いて説明しているのであって、本当に分かっていれば数式など多用する必要もないのである。
我々は現在、熱核融合やX線核融合で行われている実験と全く同じ実験を、液体窒素温度で実行し、それらと同様な実験結果(核反応生成物や中性子線および各種放射線の発生)を既に得ている。前者は数百億円の装置であるが、我々のものは手作りのたった数百万円の装置である。磁場で圧縮された重水素ガスは低温下では簡単にDD反応を起こし、D-重合体を形成して、低原子量のD-clusterやそれに伴う放射線を大量に発生させる。だが、その反応ですら加えたエネルギー以上にエネルギーを生み出す訳ではない。
図 4 (写真: 低温核融合装置)
しかし、エネルギーを付加してDD反応を起こし、D-unitが長く連鎖したD-重合体が形成されると、核子の超伝導磁束(陽子電流)が生じて、それが過剰熱や過剰電流として計測される。そのD-重合体が長鎖になると核子磁束の威力も増大して、他の原子の軌道電子を吹き飛ばし、その磁場内部の高圧気流を噴出させる。当然、これは核分裂と良く似た気のエネルギーが放出される事になる。だが、この様な現象だけを覗くと、一見核融合反応が起こっている風に思えるが、これらは科学が主張する如き核反応とは本質的に異なる。Deuteron とDeuteronが爆発的に合体してエネルギーが放出されるのではなく、それらが結合し連鎖する事によって電磁気的なエネルギーが生まれているに過ぎない。
もし貴方がどうしても核崩壊の様な大量の熱エネルギーを生産したいなら、星の重力フォースに負けない膨大な重力磁場を作って、重列元素の様な巨大なdeuteron chainの塊を作り、空間エネルギー(気)を充分に吸収したそれをランダムに崩壊させれば良い。しかし、コアと同じその超物体の核崩壊制御は至難の技であり、臨界量を上回ると、それは原子爆弾をはるかに凌ぐ超新星爆発を引き起こしてしまう。その危険性は現在のウランやプルトニウムの核崩壊と一緒である。
そもそも核崩壊の熱エネルギーを取り出して、爆弾を作る以外に一体何をするつもりなのだろうか。それで水蒸気タービンを回して電気を起こすと言うなら、今の原子炉と同じ手法であり、その原理は100年前の蒸気機関車と何も変わるものではない。単なるエネルギーの獲得に、そんな原始的な手段を人類はいつまで頼りにしなければならないのだろうか。核融合でエネルギーを取り出そうという考え方も狂っているが、その利用方法も狂っていると言わざるを得ない。我々が本格的に利用すべきものは核分裂の破壊エネルギーの方ではなく、電磁気的なエネルギーの方であって、力の場やそれを形成する力線の方を応用しなければならない。
④ 低温核融合反応
華々しい表舞台の熱核融合に対して、裏舞台の低温核融合はその発見以来、日陰の雑草の様に細々と研究が続けられてきた。この分野に於いては核融合反応など容易に起こせる簡単な反応に過ぎないが、その事実を受け入れたくない表舞台の科学者達にとっては邪魔物的な存在であり、長い間それが核反応であるとは認められなかった。なぜなら、その核反応(DD反応)からは明確なエネルギー放出が計測出来なかったからである。勿論、熱核融合の方もエネルギーは出ておらず、どちらもどちらと言えるが、しかし、つい最近になってようやく一部の科学者に固体内核反応として認められる様になった。
我々から言わせて貰えば、高温核融合も低温核融合も現代科学を基盤としており、核融合概念そのものが間違っているのに、DD反応からエネルギーを取り出そうとしている。だが、どちらかと言えば真理に近いのは低温核融合の方の考え方であり、小さな国の国家予算にも匹敵する莫大な研究費を費やす熱核融合実験はもう止めなければならない。ここでは低温核融合実験について話そうと思う。
有機物を構成する元素の多くは原子量が小さいコアレス元素(無電荷粒子を持たない原子量40以下の元素)である。それに対して金属元素の大半は内核を有する巨大元素である。それは大量の軌道電子を抱えており、有り余る磁場吸核力で原子核内部には高密度の気をプールしている。金属結晶と他の物質との違いは、それが原子の単体結晶であり、金属結合(s軌道結合)と呼ばれる特殊な結合様式で結ばれている事であろう。早い話が隙間だらけの結晶構造であって、原子間に他の元素を吸蔵し易い特徴を持つ事である。
核反応に関わる金属元素の最大の物理特徴は、何と言っても自由電子の存在と、結晶全体が囲う気密度の高さである。普段は原子結合にあずかるs軌道電子だが、磁化されると原子間に電子バイパスを形成して電流(電子磁束)を生み出し、その電界に捕獲された重水素原子が配列してdeuteron chainを形成する。また、金属原子の結晶内部には特殊な磁区(magnetic domain)が存在し、その磁区が大量の気をプールする原因になっている。この気密度が高い故に、金属原子の原子核の中には「無電荷粒子群」がその形態を留めている。これらの特徴はいずれも固体内核反応と密接な関係がある。
さて、水素ガスや重水素ガスを吸蔵した金属電極に電気を流すと、発生した電界の道筋に沿って陽子や重陽子が配列し、陽子バイパス(proton bypass)や重陽子チェーン(deuteron chain)が形成される。それは電界の作用下で一個の小さな磁石であるプロトンやデュートロンが磁極を揃えてビーズ(数珠)状に一列に並ぶという意味合いである。当然、プロトンの配列はその電荷反撥の為に間隔を置いて並ぶが、デュートロンの配列は電荷反撥が無い分、隙間のない長い重合体を形成する。いずれにせよ基盤の金属原子間に水素ならびに重水素原子核が直列状態で配列する意味に変わりはない。
図 5 (陽子バイパスと重陽子チェーン想像図)
重要な事は、低温核融合実験で起こる様々な核反応や核変換の多くが原子間に形成されたこれらの陽子バイパスや重陽子チェーンによって引き起こされているという認識である。ちなみに、重陽子チェーンが分裂して細かく切断されると、それらは一塊にくるまってD-clusterとなり、各種放射線の放射を伴って低原子量の核反応生成物(トリチウムやヘリウムなど)として出現してくる。また、これらのバイパスやチェーンの中を陽子電流と呼ばれる核子磁束(nucleon flux)が貫通して走っており、そこから吹き出す磁束線が異常熱や異常電流の発生の原因になっているばかりか、その磁束がホストの金属原子を打ち抜いて核変換を引き起こせしめている事実である。
さて、ここで図6の写真を見て頂きたい。これは我々のグループが数年前にプラズマ電解法によって実際に成功した低温核融合実験例の一つであるが、写真で分かる様に、加えた電気エネルギーを遥かに凌駕する膨大な量のエネルギー放出は、俗に言う核融合反応で起こっている訳ではない。この実験を簡単に説明すれば、重水溶液中でパラジウム電極と白金電極を用いて単に電気分解したものだが、重水素を吸蔵したパラジウム結晶間に電界の力によって発生した重陽子チェーンがその超伝導核子磁束(super-conductive nucleon flux)を放っている様子がこの写真に他ならない。
パラジウム原子間に進入した重水素原子(deuterium)は、そこに電流を流す事によって外殻電子を奪われ、裸の原子核(deuteron)となる。電界の作用下でdeuteriumは既にその磁極を揃えてビーズ状に配列しており、電子を略奪されて原子間距離が縮まると同時に、deuteronは互いの磁極で引き合ってD-重合体chainを形成する。この重陽子chainが超伝導磁束を放ってホストのパラジウム原子を打ち抜き、一連の振動波放射(光)や核エネルギーの放出(気)を行うのである。無論、磁束によって打ち抜かれた金属元素は外殻電子を失って裸の原子核と変貌し、簡単に核融合や核分裂を行うのであって、超伝導磁束が核変換のトリガーに成っている事実は憶測するまでもない。
図 6 (写真: プラズマ電解法による電気分解実験)
この実験から発生する各種放射線のエネルギー量を正確に計測する事は不可能であるが、僅か数十mmAの電流を加えて金属電極を一瞬に溶解してしまう数千度から数万度の高熱が発生する訳も無く、またγ線や中性子線の発生や放射性の核反応生成物の発生を考慮すれば、明らかに何かの核反応が起こった事は確実である。但し、その核反応とは一般に認識されている様な核反応ではない事は既に記述した通りであって、それは粒子の結合エネルギーが放たれるのではなく、粒子を結合させる事によって誕生する二次的な“電流”エネルギーに他ならない。
⑤ 電流とは何か
核子磁束(陽子電流)と言っても、その実在の有無はともかく、今の科学界に存在しないそんな言葉自体が受け入れ難いかもしれない。だが、この一番大切な事を知らないから現代科学が低迷しているのであって、これが分かれば全ての謎が一瞬に解けてしまうのである。ここでは先ず今まで誰も解いた事の無い電気の謎から説明したいと思う。
承知の様に、電気は未知の力であり、その本当の正体は誰も知らない。一般に、電流とは電子の移動や正孔(ホール)の移動によって生まれる電子電荷の流れだと言われているが、その真実の姿は全く知られていない。物体の中を数兆個の電子群が徒党を組んで流れる筈も無く、また電子の抜け穴であるホールがそれ自身で移動して歩く訳もない。人間が走る程度の速さで走る電子速度でどうして物体を振動発光せしめてジュール熱を発生させる事が出来ようか。いや、それよりも電気と電流は果して同じものなのだろうか。それらがプラスからマイナスに流れるという話も本当なのだろうか。いつもながら、科学の説明には甚だ疑問を感じざるを得ない。もしそれが本当なら、高圧電線を切断したら電子やホールが飛び出してくる筈であり、それが検出出来ないのは一体なぜだろうか。
電気の話を納得行くまですれば、それだけで本3冊分になってしまう。従って、ここでは簡単に結論だけを述べるに留めるが、それで納得して頂けるなら幸いである。我々が通常、電気と呼んでいるのは“電圧流(大電流)”と呼ばれるものであって、それは発電所の変圧器から生産される磁場の中心磁束の方である。それが電線を磁化して電子を配列せしめ、膨大な量の電子バイパスが形成され、その中を電子の中心磁束が貫通していく。この電子の中心磁束の流れをまとめて“電流(小電流)”と表現している。つまり、電気とは大電流によって引き起こされる小電流という二本立てのカラクリ構造になっているのである。
一般に、化学電池から生産される直流電気はこの電子磁束であり、それらは数珠状に電子が配列した電子バイパスから繰り出されるものである。科学はボルタの電池の電解溶液中に無数の電子バイパスが形成されている事実を知らない。この電子バイパスの存在を実感したいなら、放電管や蛍光灯の陰極線を見ればその確かな形態を実際に目で確認する事が出来るだろう。陰極線とは1本の棒磁石と化した電子バイパスの集団であり、そこから放出される電子磁束が羽根車を回転させ、陽極に影を投影しているのである。JJ トムソンが発見したものは電子ではなく電子磁束の方である事に気が付かねばならない。
小さな丸型磁石をNS結合させていくと、それは一本の棒磁石となる事は承知の通りである。であれば、その丸磁石の中を貫通して流れる磁石の中心磁束流を我々は何と表現すれば良いのだろうか。それは磁石電流とでも表現するのが妥当なのだろうか。磁石と同じ様に地球を10個並べれば、その地球バイパスの中を地磁気の中心磁束(dipole flux)が貫通していく。我々はその磁束流を一体何と命名すれば良いのだろうか。
この様に、陽子バイパスが形成されれば陽子の中心磁束が、そして重陽子チェーンが形成されれば核子の中心磁束が誕生するのは自明の理であって、これらは現実に実在する本当の電流に他ならない。これらの電流は通常の電子電流とは少し質が異なる為に、陽子電流あるいは核子電流と分けて呼ばれている。いずれにしても電気とは光速度で伝搬する磁場の中心磁束の流れの意味であり、これらが原子の磁場を打ち抜いてジュール熱が発生している。電気も磁気の一種、いや磁気そのものである事は勿論、電子が持つ磁荷量を電荷量という名で呼んでいるに過ぎなく、磁荷量も電荷量も結局同じものに他ならない。
⑥ 超伝導とは何か
陽子バイパスと重陽子チェーンは同じものではない。両者は同じ核子の配列であるが、前者は陽子だけの配列であり、間隔の開いた配列状態であって、通常の核子電流が流れている。一方、後者は重水素原子核の配列であり、中性子と陽子から成り立つものであって、隙間なく重陽子が重合した鎖状の物体である。ここに流れる核子電流は常温下でも磁束の漏れがない完全無欠の「第一種超伝導性」を示す。
それと同様に、電子バイパスも、常温下では電子磁束の漏れが多い通常伝導性を呈示するが、電子と反電子が結合したπ-電子の重合体チェーンは重陽子チェーンと同じく、常温下でも完全無欠の第一種超伝導性を示す。しかし、通常伝導性を示す電子バイパスや陽子バイパスであっても、超低温下では第二種超伝導性を示すばかりか、更に極超低温下に於いては第一種超伝導性をも示す。つまり、温度が下がれば下がるほど、電子同士や陽子同士の電荷反撥が抑制され、バイパスの配列間隔が至近距離となり磁束の漏れが無くなるのである。無論、高温になると電流が流れ難くなる理由は、個々の電子の運動が活性し、電流の通り道である電子バイパスを維持出来なくなるのがその原因である。
この様に考えていくと、超伝導とは一体何であるか、そして常温下で電流の超伝導状態を起こす為にはどの様な手段を取れば良いのかが見えてくる。つまり、重陽子チェーンやπ-電子チェーンを作れば、常温超伝導を利用し、その最も有益な超伝導磁界を手に入れる事が出来るのである。電子電流の超伝導磁界は磁力線を遮断する“反磁性(マイスナー効果)”を呈示するが、一方、核子電流の超伝導磁界は驚く事に、重力を遮断する“反重力性”を示す。つまり、それは超伝導核子磁界の中では物体の体重が零になるという話である。
しかし、残念な事に、今の科学は電子バイパスを知らないばかりか、核子電流の存在も、また陽子バイパスや重陽子チェーンの存在さえ知らない。また超伝導の意味も知らなければ、その特性も知らず、用途価値すら分からない盲目状態である。早い話が、それらが無限量の永久電気や永久動力を生み出す素材である事を知らないのである。この分野が発達すれば、化石燃料を使用する必要もなければ、原始的な磁石発電機や危ない原子炉や、あるいは直ぐ爆発する垂直ロケットを使用しなくても良いのであって、人類は一挙に宇宙時代を迎える事が出来るのである。電気を正しく理解しているかしていないか、たったそれだけの事で技術面ではこんな大差となって現われてくると言わねばならない。
⑦ 電子磁束と核子磁束
重水素ガスを吸蔵した純粋なパラジウム電極に電流を流すと、ガスを大量に吸い込んだ金属表面には核変換が起こって、パラジウムの核異性体の存在比が大幅に変化する事は勿論、数十種に上る大量の新生元素が誕生してくる。驚く事に、その新生元素の中にはホスト基盤であるパラジウム原子量の倍の元素も誕生している。そして不思議な事に、それらの新生元素の存在比は宇宙の元素存在比であるクラーク数と極めて良く一致する。これは一体どういう事だろうか。純粋なパラジウム元素がなぜ鉄やカリウム、あるいはヨウ素や金に変貌してしまうのだろうか。
この様な不思議な現象に対して、用意出来る解答は2種類考えられる。その一つは、パラジウム原子間に形成された長鎖の重陽子バイパスが重列元素の様に分裂崩壊して新生元素が誕生してきたという考え方である。これならば星のコアの中で起こる現象と全く同じであり、新生元素の存在比がクラーク数と一致するのもうなずける話である。だが、その仮説には少々無理がある。なぜなら、重水素ガスの代わりに単なる水素ガスを吸蔵させたパラジウムでも同様な核変換が観察出来るからである。それに、重列元素の重陽子チェーンと金属結晶中の重陽子チェーンは性質が異なる。同じ重陽子チェーンでも、前者は電子を備えた無電荷ユニットで形成されているが、後者は電離して電子を持たない有電荷ユニットで形成されている。つまり、陽子の電荷反撥がある分、大変切れ易いチェーンであり、長鎖の重合体を形成出来ないからである。
もう一つの考え方を述べると、形成された重陽子チェーンが繰り出す核子磁束がホスト基盤のパラジウム原子を打ち抜き、その電子層を破壊して裸の原子核にしてしまったという仮設である。核融合が簡単に起こらない理由の一つに、原子の外殻を周回する軌道電子の磁界が邪魔して融合を難しくしている例が上げられる。防御壁を持たない裸の原子核だけなら、核融合も核分裂も、あるいは中性子吸収も比較的簡単に起こり得る。しかし、核子磁束に電子層を吹き払うほどの力が本当にあるのかどうか疑問が残る。
図 7 (新生元素の存在比グラフ)
ここで、電子の軌道磁界や核子磁束について良く考えてみたい。原子は全て外殻に軌道電子を周回させており、その軌道磁界、つまり電子の角運動磁界に包まれている。磁場の掟とは、同質磁界は互いに反撥するというもので、電子の磁界は他の電子の磁界を受付けない。だが、電子の磁界と言っても種類がある。電子自身が持つ磁界(フォゾン角運動磁界)もあれば、軌道磁界もあるし、電流の角運動による磁界(電磁場)もある。これらは全て電子系の同質磁界と言える。つまり、これらの中心磁束は皆、原子の皮膜を打ち破る事が出来ないのである。
しかし、核子の中心磁束ならばどうだろうか。原子に対して高速度の電子を打ち込んでも大概の場合はその軌道磁界によって跳ね返されてしまうが、それが陽子や中性子ならばどうだろうか。陽子は電荷を持っているが、その電荷は反電子のものであり、電子とは正反対の質を持つものである。高速の陽子は軌道磁界を打ち破って原子核に到達出来るし、また電荷の無い中性子は勿論もっと簡単に貫通出来る。つまり、核子磁束は大した抵抗もなく楽々原子の軌道磁界を打ち破る事が出来るのである。
従って、パラジウム電極の核変換のトリガーになるものは原子間に形成された陽子バイパスや重陽子バイパスが放出する核子磁束であって、その放射を受けた大量の裸の原子核がそれら自身で自然な核反応を行っていると考えられる。
⑧ 重水素ガスから固体を作る
重水素ガスを圧縮冷却していくと、最終的には液体になる事は承知の通りである。しかし、ガスから直接重水素の固体が作れると言ったら驚くだろうか。実際、我々はまさにその実験に取り組んでいる最中である。重水素の固体と言っても、重水素原子の固体ではなく、重水素原子核の固体であり、超密度の原始物体、いわゆる重陽子チェーンの事に他ならない。この外殻電子を持たない原子核だけの超物体は星のコアの重列元素と同じであり、無電荷ユニットの長鎖の重合体である。当然、コアと同じく臨界量を超えると超新星爆発を起こす危険な物体な為に、極めて慎重に実験を進めざるを得ない。
この実験を簡単に説明すれば、磁場の中でD2 ガスを圧縮冷却し、核反応(K殻電子捕獲=β− 崩壊)を誘発させて核融合反応を起こすというもので、低温下という条件を除けば基本的には高温核融合実験と何も変わらない。強大な磁場プレッシャーを付加すれば、核反応が全域に及び、D2 ガスの固体が出現するが、通常の磁場圧であれば部分的な核反応で終わる。後者の実験の再現性は高く、核融合反応の証である中性子バーストや副生産物として様々なDX 重合体の検出に成功している。無論、付加する磁界は磁石の磁界ではなく、重力磁界と同じ静止電磁場、つまり空芯コイルの電磁場を特殊な方法で使用している。
図 8 (中性子バーストのグラフとリアクター写真)
核反応生成物であるDX 重合体の質量は磁場圧によって異なるが、一般的にはD20からD40 が普通であり、その物量は固体内核融合のD2からD10と比較すると遥かに大きい。これらのDX 重合体は勿論、重陽子チェーンの断片がくるまって一塊になったもので、元素に進化する以前のD-clusterとして存在している。当然、強大な磁場圧を付加して長鎖の重陽子チェーンを作れば、それが崩壊する際には地球上には存在しないD150を超える超ウラン母源元素とおぼしき巨大なクラスターも誕生してくる。
現在はD2 ガスをサークル管に詰めて環状のdeuteron chainを合成し、反重力を呈示する“超伝導磁界”を生み出す実験“[D-tube実験]”に取り組んでいるが、技術面の難しさと研究費の問題もあって、その実験にはまだ成功していない。しかし、世界の技術者が本格的にこの実験に取り組めば、技術上の問題は直ぐクリアー出来ると思われるのであり、無燃料・無排気の永久駆動力を持った電気自動車が自由に空を飛び回る未来社会はもう目前に来ていると思われる。放射能の危険と核爆発の危険を犯してわざわざ崩壊エネルギーを取り出さなくても、核子の重合体のままで利用する方法を考えなければならない。
E 粒子と磁場
① 基礎粒子の実体
そもそも電子や陽子は帯電したパチンコ玉状の物体ではなく、惑星系や太陽系や銀河系と同じ渦磁場を備えた渦系物質であって、中心核にコアを抱いた渦流の姿こそその本当の正体に他ならない。目に見える地球とは地球渦系の中心物体(コア)であって、外から見える本当の地球(地球磁場圏)とは半径が約2000万Kmにも及ぶ巨大な磁界である。それと同様に、我々が陽子だと思っているものは陽子の磁場圏であって、中心核に存在する陽子のコアはその数万分の一の大きさに過ぎない。電子や陽子は極小サイズの渦系物質であり、それは小さいだけで地球や太陽と何も変わらない渦磁場の回転体と言えるだろう。
基礎素粒子の実体が大気の渦巻きと同じ渦磁場であるなら、その回転体の中心点には吸核力が向心しており、そこから垂直に延びる磁気ダイポールからは回転磁束が吹き出している筈である。もし、それが低気圧と同じ反時計回転(αスピン)ならば、磁束の出口であるN極は回転面の上方に位置し、またそれが高気圧と同じ時計回転(βスピン)ならば、そのN極は回転面の下方に位置するだろう。電子や陽子が固有のスピンを持ち、それが一個の丸磁石としての性質を呈示し、互いに配列重合して磁束流(電流)を生み出すという特徴は、それが空間媒体(気)の角運動から生じる「力の場」である証明に他ならない。
図 9 (陽子磁場の構造想像図)
陽子や中性子が天体と同じ渦磁場であるなら、その子星とは電子や反電子であって、地球がその子星である月を内軌道に従えている様に、もともと陽子は反電子の母星であり、また中性子は電子の母星と言える。母星の磁場の特徴は、子星の軌道磁界(電磁場)に支配されており、月の電磁場によって地球が支配され、様々な影響を受けている事は承知の通りである。それと同様に、陽子の磁界はその子星である反電子の軌道磁界に磁化されており、陽子=反電子と言っても間違いではない。無論、イントロン(陰電荷中性子)は電子の軌道磁界に磁化されており、磁界の性質は電子そのものと同じだと表現しても構わないだろう。母星の性質は子星によって変化するのである。
平たい言葉で表現すれば、陽子とは一個の電磁ボールの様な形態を呈しており、地球の様な固体の殻を持った物質ではない。固体の部分は陽子の渦流の中心点に気の粒から出来た小さなコアを持つだけである。そのコアとは当然、陽子渦流の重力フォースによって圧縮された状態であり、その中だけでしか実体を囲えない仮の物体である。そこから飛び出したコアは実に100億分の1秒という短期間で分解して気に帰納してしまう。それは電子渦流のコアも同じであり、それらは瞬間の実体しか持たない故に、瞬間粒子群と呼ばれているが、科学では前者をハドロン、そして後者をレプトンと称している。だが、それらの物体は単なる気の塊に過ぎなく、性質を備えた粒子(物質)と呼べる様な存在ではない。
一個の粒子の形態を支え、その質を奏でて、そしてその生命作用を呈示出来るのは、つまり陽子が陽子として存在を獲得出来るのは、その渦流が囲う渦磁場のお蔭に他ならなく、その様な意味では磁場こそ物の命その生命当体と言える。この世の万物がたった4種の基礎素粒子から出来上がっている事を考えれば、絶対的に確かな存在と呼べる物は無く、皆気の運動から成り立っている。そしてその運動が終われば、全ての物は気に帰納するのであり、物の存在自体が運動によって具現する“仮の姿”と言えるだろう。
さて、四つの基礎素粒子と、地球や太陽という天体物質は気の渦流が生み出す渦系物質であるが、原子に渦流は存在しない。それらは渦磁場の代わりに電子を公転させ、“軌道磁界”を生み出し自己の生命としている。鉄原子が鉄としての性質を具現出来るのは、その軌道電子が生み出す軌道磁界のお蔭である。鉄はそこで自己の意識をまとい記憶力を持ち、事物に作用を与えているのである。つまり、鉄原子の命は肉体(原子核)の外側に存在するのであり、その構造様式は万物共通である。無論、人間もその例外ではない。
② 角運動と力の場
電子が公転運動(orbital movement)しただけで、どうして立体的な“力の場”が形成されるのだろうか。そう質問しても、その正解を述べられる者は誰もいない。なぜなら、世界中の誰一人としてその答えを教えて貰った経験が無いからであり、また自分の頭で考えようと試みた人間もいないからである。しかし、物事の道理から判断しても、回転運動(rotatory motion)の種類は多いが、皆同じ原理で動いている筈である。原理を考えるのは何もニュートンの様な天才の専売特許ではない。ニュートン以来350年間が経過しているが、残念ながら新しい運動原理を求める意欲のある理論家は今まで出現しなかったと言える。
回転運動が立体的な作用力を持つ事実は高低の気圧や台風や竜巻を見ても明らかである。例えば、台風の実体とは単なる大気の平面渦であるのに、その作用力は渦を直径とした球体の全域に及んでいる。平面回転がなぜ立方球状の力の場を囲うのか、力の発生メカニズムと、それが形成する場の構造について考えなくてはならない。
ニュートンによれば、角運動(angular motion)する物体の向心力(向心加速度)は回転の中心点に集まると言う。別にその考え方に異論はないが、中心点に集約したその力は一体どこへ行くのだろうか。私には力がただそこでジッと静止しているとはとても思えない。中心点に集約した力はある特殊な循環運動(circulatory movement)を行っていると考えられるのである。なぜなら、「角運動量保存則」を考慮すれば循環以外に考え様がないからである。では一体どの様にして力の循環運動は行われているのだろうか。
左巻きの低気圧渦を見ると、その回転面を真上から覗いて、上方に向かって力が吹き出していく。一方、右巻きの高気圧渦はその反対の下方へ向かって力が吹き出していく。という事は、回転の中心点に集約した力がまず始めに“力の束”となって回転軸に沿って垂直に吹き出し、“力の場”を形成すると考えられる。最初に吹き出した力の出口をN極とすれば、それが場を形成しながら反対のS極(入口)に吸収されるという循環行程を行っていると考えられる。当然、S極とN極を結ぶダイポール・パスの中を力の束が貫通しており、その回転面(赤道)から新しい力が次々と注入されている事は想像出来る。
図 10 (回転方向と中心磁束の方向)
所で、力の場には必ずこうした力の出口と入口という二つの極が存在しており、これらをモノポールとして単体分離する事は不可能である。今の科学ではN極やS極だけの単体磁極が存在すると考えられているが、その様な馬鹿げた発想をする理由は力の場(磁界)が良く分からないのがその原因だと思われる。だが、こうした唯物的な発想は別にモノポールだけの話ではない。中間子理論や共有結合という粒子と粒子が結合する接合概念自体が狂っているのである。
電子が左巻き公転(α-公転)すると、形成されたその軌道磁界の磁極は、回転面を上から覗いて上方にN極が生じ、またその下方にS極が生じる。当然、もし電子が右巻き公転(β-公転)すれば、反対に上方にS極が、そしてその下方にN極が生じる。もし、α-公転する二つの水素原子が在ると仮定して、それらが結合して水素分子になる為には、NSの磁極を合わせて縦結合(直列)するか、さもなければ片方が反転し、仮のβ-公転を囲って横結合(並列)するか、そのどちらかしか結合する方法は無い。それは2個の磁石を保存する時の方法と一緒であって、通常、水素原子は後者の横結合の方で連結している。
つまり、水素原子はその外殻電子の力の場(軌道磁界)で結合しているのであって、電子を共有し合って結合している訳ではない。それは陽子と中性子も同じであり、α-spinの陽子とβ-spinの中性子は互いに反粒子であり、その結合は磁荷反撥が無い分縦の直列結合を選択するが、NS結合している事に変わりは無く、中間子を媒介にして結合している訳ではない。粒子と粒子の結合は皆こうした力の場の磁極結合によって結ばれており、粒子と粒子が他の粒子を媒介にして結合するなどという事は有り得ない話だと言わねばならない。この宇宙に於いて、物と物とを接合する為には、紐で結ぶか、あるいは接着剤で付着させるか、さもなければ磁気的な力で結び付ける以外に方法が無い。
さて、回転運動が生み出す垂直力の進行方向は左ネジや右ネジの垂直ベクトル力と同じであり、これは全ての回転運動に共通するものである。しかし、力(active force)が作用すると、その反作用としての力(reactive force)が生じてくる事は承知の通りである。角運動が生み出す力の場とはいわゆるこの反作用力の場に他ならない。そもそも作用力も反作用力も本来は方向を備えた直進ベクトルなのに、なぜ角運動の様な回転運動が存在するのだろうか。カーブのかかった力など本当に実在するものだろうか。これから回転運動の本質を探ってみようと思う。
③ 回転運動と四角形運動は同じ
回転運動(円を描く運動)と四角形運動(正四角形を描く運動)が同じ運動であると言うと驚かれる方も多いだろう。しかし、両者を角運動(角度を刻む運動)として捕らえれば、それらが刻む角度は同じ360度であり、両者は本質的に同じ運動に他ならない。正四角形が回転し、その角が取れて丸くなれば真円になる事は自明の理である。
別に超紐理論の肩を持つ訳ではないが、宇宙に最初に出現した力は直進力(direct force)であり、直進ベクトル(direct vector)の世界である。無論、その直進運動(direct motion)とは超密度に圧縮された気が爆発して宇宙が開闢する事(ビッグ・バン)に起因している。放射状に拡散膨張する気の直進力が「四諦摂理:quaternion principle」3) に基づいて四角形運動(square motion)を起こし、それが全ての回転運動(rotatory motion)の原形母体とも言える渦運動(vortical motion)へと発展するのである。つまり、最初から円運動(circular motion)が存在したのではなく、その元初の形態は90度の角を持った四角形運動であり、それは1本のベクトル・フォースが3箇所で直角に折れ曲がって作る正四角形であって、要するに、宇宙とはもともとの姿が直線の世界だという話である。
「四諦摂理」とは仏法の輪廻原理(principle of metempsychosis)に由来するもので、回転もしくは循環の法理と呼ばれる宇宙哲理(law of universe)である。それはこの世の万物万象が、異なる四つの要素、もしくは四つの段階行程を経て輪廻するというものであり、数学や幾何学にも当てはまる奥深い普遍の原理である。四諦摂理は「陰陽原理:yin-yho principle」4) と双璧する自然界の二法であり、両者は宇宙の全ての原理の根幹となる原理の原理たるべく本源哲理と言えよう。この二法の詳しい説明はここではしないが、全ての運動がこの様な絶対原理に基づいて行われている事を認識して頂きたいと思う。
さて、一本の直進ベクトル力が直角に反射したとしたら、その反作用である合成ベクトルは一体どこに入力するのだろうか。正四角形を描く運動をした時、その四つ角から生まれる反作用ベクトルは当然四角形の中心点に入力していく。だが、中心点に入力した反作用力はそこでただジッと静止している訳ではない。それは中心軸に沿って外界へと吹き出し、立体的な「三角形運動:triangular motion」を行う。その三角形運動の結果として出来上がる物が二つのピラミッドを合わせた様な“正八面体(regular octahedron)”である。この正八面体こそ直線力が描いた力の場の基本骨格図であり、それが回転によって遠心力性のカーブが加わり、球体状の力の場が創造されるのである。
図 11 (四角形運動と三角形運動図)
目に見えない球体磁界の形状原型は正八面体であるという話だが、それは鉱物結晶の形を見て貰えば簡単に想像がつく事である。スピンを止めた瞬間の気の粒や陽子の形状はほぼ正八面体を呈している。だが、宇宙の物は皆回転しており、あまねく球形を呈していて、その球形を作り出す球体磁界は原則的に四角形(円)と三角形(半円)から構成されており、角を持った直線形の形状がその原型に他ならない。当然、回転運動の母体である渦運動も回の字型の四角形運動であり、それが故に銀河系や太陽系は長楕円形の形状を呈している。ケプラーの第1法則として馴染みが深い惑星の長楕円軌道は、太陽系自体が単なる円運動ではなく渦運動を起こしており、それが描く力の場は正八面体ではなく、一辺が特別長い変形八面体であるというのがその理由である。
いずれにしても回転運動の向心力がなぜ回転の中心点に入力するのかという疑問は、それが角を有した四角形運動であるという事であり、元よりそれが角運動と呼ばれる由縁である。
そして、角運動の中心点に入力した四本の反作用力がN極から吹き出し、三角形を描いてS極に戻るという循環行程を辿る結果、正八面体(球形)の力の場が誕生してくる。これは二次元的な平面回転運動が三次元立方の球形運動を生み出すという宇宙の秘儀とも表現出来る大変に意義深い運動と言えるだろう。

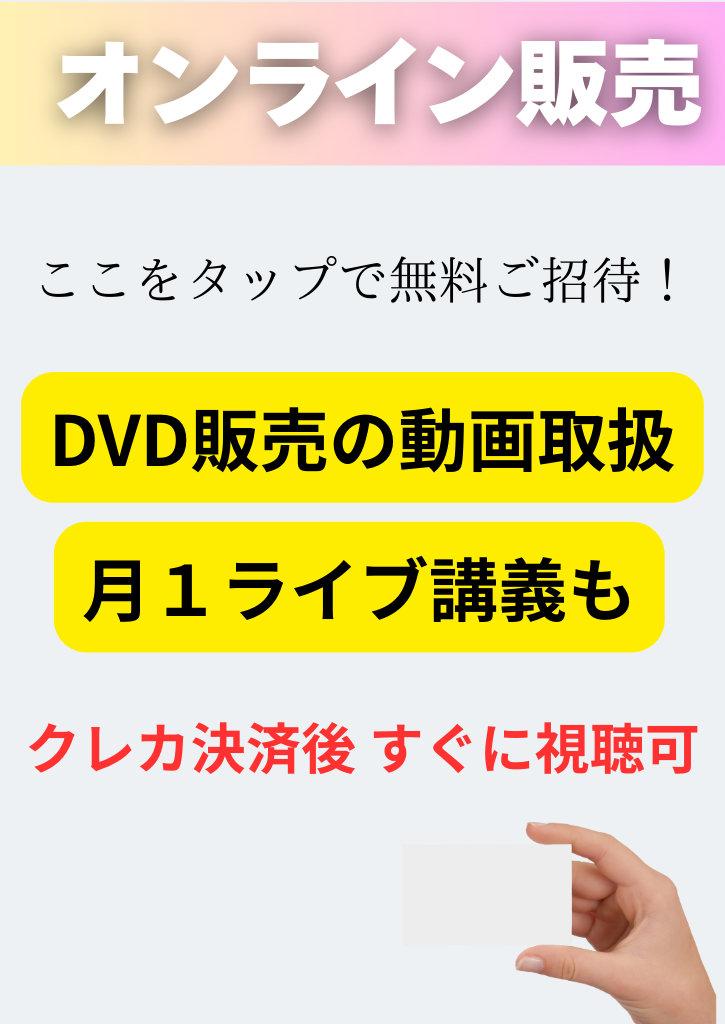





Comments are closed