〈有機化学の基礎編(その1)〉
① 渦巻宇宙論と物質宇宙論
生物体を構成する有機材料とは宇宙の一体何処で作られているのでしょうか。そもそも宇宙で最初に生産される物質とは四つの基礎素粒子から構成される「重水素ガス」であり、それらのガスが大きな天体渦巻の中心点に圧縮されて「中心物体」である星のコアが誕生してきます。特に太陽系内や惑星系内には直径が数cmから数百kmに至る大量の「岩石渦」が誕生しており、周囲の重水素ガスがこれらの渦巻に吸収されて、その中心点には大小様々な物質が生まれてきます。直径数cmという小さな空間渦には主に原子量が20以下の低位元素が発生し、それらは「氷塊(H2O)」だったり、「ドライアイス(CO2)」だったり、あるいは「メタン(CH4)」だったり、また「アンモニア(NH3)」だったりしますが、これらの星間物質が有機物の原材料として惑星渦巻の内部へと取り込まれていく事になります。木星や土星の原始大気が星間物質の組成である事は承知の通り、もし惑星の表面温度が液体の水でいられる環境ならば、炭酸ガスやメタンガスやアンモニアガスを吸収した原始海洋(生物の源)が誕生していたと思われます。
ところで、一体どういう仕組みで天体の渦巻は空間に発生した星間物質を集められるのでしょうか。承知の様に、渦巻の系内に物質が入ってくれないと渦系は中心点に物質を集約できません。惑星渦は自己の系内に発生した星間物質だけでは材料の獲得量が十分ではなく、太陽系の幅広い領域から材料を集めてくる必要があります。海洋を作るだけでも膨大な水分子を獲得する必要がある事は言うに及びません。実は渦巻にも馬力の差が存在し、発生したばかりの若い渦巻は「求核渦」と呼ばれる台風の如き勢いのある渦巻ですが、勢力が衰えた老化渦は低気圧の如き落ち着いた渦巻であって、等速度円運動を基盤とする現在の天体渦が大人の渦巻の状態であると言えます。これは宇宙年齢の話ですが、銀河一般科学によれば、求核渦の時代が約30億年間続いて(ガス雲の時代)、恒星系の中心点に最初のコアが誕生してから約100億年以上も経過しているのが現在の宇宙の実態(累計年齢130億年)であると見積もられています。片道行程が180億年とされるビッグ・バン開闢宇宙の運動寿命を考えれば、現在の宇宙とは盛りが過ぎた60歳代ぐらいの宇宙であると言えましょうか。
また、地球科学に於いては、宇宙の形状とは「定常宇宙論」的な概念と「進化宇宙論」的な概念という2種類に分かれていますが、実際の宇宙の姿とは「拡散膨張期(求核渦の時代=前半期)」と「安定衰退期(安定渦の時代=後半期)」に分かれており、現在の宇宙とは後者の状態にあります。観測できるあらゆる天体が「赤方偏移」を示している事実、また宇宙の至る所から観測できるマイクロ波の存在事実、これらの事実を光の「ドップラー効果現象」や「3K背景輻射現象」から推論すれば、宇宙は明らかに膨張しており、現在の地球科学は「宇宙膨張説」に傾いている事は承知の通りです。「宇宙は確かに膨張している様だ、しかしなぜ空間に忽然と重水素ガスが発生してくるのか、それが良く分からない」というのが地球科学の泣き所でした。我々の意見は「確かに宇宙はビッグバン爆発による膨張宇宙であったが、今は膨張していない」という考え方であり、また重水素ガスの発生に関しても、単なる物質概念の「勘違いだろう」というのが、我々の考え方です。現在の宇宙は「膨張していない」という説明に対して違和感を覚える方も多いだろうと思いますが、地球人は光世界が描き出す「時空トリック」に誤魔化されていると言わざるを得ません。
天体観測器で見える現在の宇宙の姿とは「光マジック」によって描き出された「過去の映像(遺物)」に過ぎなく、地球人は宇宙の前半期の映像を垣間見ているに過ぎません。クエーサーや活動銀河の実映像とは、それは100億年も前の過去の姿であって、今現在の宇宙の本当の姿ではありません。天体望遠鏡から見える宇宙の姿とは過去のビデオ映像と一緒、人類はその事実に気が付くべきなのです。承知の様に、100億光年の彼方の映像は100億年後でなければ地球には届かないもの、なぜそんな単純な原理に気が付かないのか、浅はかな西洋科学(野蛮人科学)に洗脳されてしまった浅はかな龍神島民族に対して、我々は「君の頭は大丈夫なのか?」と心配せざるを得ません。また、「物質概念」に関しても、なぜ1個の物体陽子が「磁気モーメント」を有し(磁石として作用する=NSの極性を示す)、固有の電荷量や固有のスピン量を備えているのか、一体どうやって球体の形状が維持されているのか、あるいは陽子と中性子がなぜ硬く結合できるのか、原子核を硬く結び付けている核力とは一体何の力によるものなのか、全く解答を導き出せない状態にありました。
そこに登場してきたのが数学家が編み出した詭弁理論である「量子力学(オリオンの似非理論)」と、それを実験で裏付けようとする「電磁気学」や「素粒子物理学」です。素粒子の電荷量を説明する為に「クォーク理論」を設けて、粒子と粒子の結合に「接合子理論」を想定し、また原子核の凝集力に関しては「トンネル効果理論」を、電流に関しては「ホール効果理論」を提唱して、説明不能な現象に対しては半ばゴリ押し状態で無茶苦茶な理論を展開し、実際に有りもしない仮想粒子までデッチ上げているのが現在の地球科学の実情です。別に数学の力を借りなくても、この宇宙の謎は考え方を改めるだけで全て解けるのであって、素粒子そのものが1個の渦状物質であると考えれば、後は常識で理解できる矛盾無き宇宙となります。我々は宇宙の真実を伝えているだけの話であって、地球人が築いた文化を根こそぎ破壊しようとしている訳ではありません。真理に目覚めれば地球の未来はもっと明るくなる筈、具体的な未来の形が見えてくるからです。
さて、我々の太陽系(SUN太陽系)では若い求核渦の段階で、系内に発生した大半の星間物質は渦巻の中心点付近に集められて、太陽磁場圏の重力圏内(火星軌道よりも内側)には濃密な星間物質が集約されていました。特に第三惑星の地球と第二惑星の金星は両方とも「水の惑星」だったのですが、金星は今から35億年前に惑星の運動寿命が閉じて、また衛星の月も今から20億年前にはそのスピンを停止させています。地球と金星は同じ公転軌道を周回する惑星同士なのに、早期の段階で互いに「磁束の糸」で引き合って結ばれ、金星は地球に対してデングリ返った逆様状態となりました。太陽系の中では金星が唯一逆向きのスピンを呈している理由がここに在ります。それは衛星の月も一緒であり、地球の子星である月も、まるで電子の如く磁極を反対向きにして地球と「磁束の糸」で結ばれています。こうした事象は粒子の世界では当たり前に起こる現象ですが、実は天体の世界や気象の世界でも当たり前の様に発生している渦巻現象の特徴なのです。
太陽系内に発生した星間物質(生命素材)が特に内側の重力圏に集約される事は理解できると思いますが、それにしても地球が獲得した有機材料の物量が膨大であり、群を抜いている事を考えれば、これには逆向きスピンの金星や月が大きく関与していたと推察ができます。有機化学の話なのに、有機素材の成分の話ではなくいきなり天体の物理法則の説明になりますが、惑星(電子)という一つの有電荷粒子が一点を中心とした回転運動(公転運動)を起こす場合、そこには「軌道磁界」と呼ばれる特殊な「磁場(球体)」が形成されており、その磁場(力場も含む)の「求核力」によって物質が一点に集約されるという宇宙法則が存在します。惑星の公転運動の場合は星間物質の集約力の話となりますが、電子の公転運動の場合は原子や分子同士の結合力の話となる為に、有機物という高分子を扱う有機化学にとっては「粒子概念」に関する物理学上の基礎知識は必要べからざるもの、宇宙法則を正しく理解しないと現在の地球科学の様ないい加減な学問になってしまいます。
そもそも渦磁場の系内重力は回転運動と密接に関連しており、「位相運動(phasic movement)」を起こしています。つまり、圧縮期と弛緩期を繰り返す「吹子」の様な運動を呈しているのが特徴であり、これは天体の「潮汐力」と呼ばれています。系内重力とは渦巻の力場を奏でる12個の力学テトラ体から生じる「力」であって、第6力場(第6テトラ体)を中心にして、それ以内(第1から第6まで)を重力圏(求核力圏)、それ以外(第7から第12まで)を磁力圏(斥力圏)という二大構成であり、それが回転運動と絡み合って力場の圧縮期と弛緩期が交互に出現してくるという性質を醸し出しています。その様な意味では、系内重力とは周囲の物体を渦巻の中心点に集める力としては強弱があって安定していない理由から、常時的に作用してくれる安定した求核力が必要である事は分かって頂けるものと思います。恒星や惑星は「小星」を抱えて「軌道磁界」という特殊な「力の場」を囲って星間物質を安定吸収している訳です。非常に難しい話で恐縮ですが、これが渦磁場の妙技と言えるものです。ちなみに、月と同じサイズの物質衛星を作ってそこに人間が立てるのかと言えば、降り立つ事は不可能です。既に回転を停止したとはいえ、天体には力場(テトラ体)の一部が残存しており、金星には三つのテトラ体が残っており、また月には四つのテトラ体が残留していて、人間が宙に浮く事なく歩行できる事は承知の通りです。
原子核に対する電子の公転運動と、地球に対する衛星(月)の公転運動は基本的に一緒なもの、公転運動(軌道運動)そのものに深い宇宙法理が存在しており、渦磁場の「重力」とは異なる、軌道磁界の「求核力(向心力)」という別種な物理作用が生じてきます。渦磁場が系内重力を有するのは当たり前の話ですが、原子核の周囲を公転する外殻電子層も重力と良く似た求核力を中心点に対して向心させており、中心点に対して物質を安定的かつ均一な力で圧縮する作用を備えています。下図に示したのは陽子(プロトン)と外殻電子(エレクトロン)の関係性ですが、電子は一定の軌道を公転運動しているだけなのに、そこに形成された軌道磁界とは陽子の中心点に対して求核力を集中させており、気の粒を圧縮して中心物体(バリオン)を形成します。原子核に秘められた凝集力の強さとは、原子核の粒子同士の引力のなせる技ではなく、外殻電子が形成する軌道磁界に凝集力の原因があるという話でしょうか。また、外殻電子の軌道運動とは基本的に二次磁場を形成する運動であって、軌道磁界には必ず磁束の出入口(N極とS極)が回転面の垂直の方向に形成されます。まあ、それが故に我々は「軌道磁界」と命名している訳ですが、この運動法理の真の意味合いとは、小さな電子が巨大な電子に置き換わった意味であり、軌道磁界そのものが1個の電子として振る舞うという話なのです。

「意味がお分かりでしょうか?」、1個の陽子と外殻電子の周回運動は「陽子が水素原子になる」意味ですが、その本意とは「小さな電子が1個の巨大電子に成長する」といった意味合いであり、水素原子の電荷量は電子1個の電荷量と一緒、水素原子とは電子の「化物(化身)」に過ぎないのです。当然、水素原子の内部の何処を探しても、軌道電子の姿を見る事はできず、一見、何処にでも電子が存在しているかの様に見えます。従って、地球科学は電子の位置を確率で示している訳ですが、電子はまるで月の如く一定の水平軌道を等速度で公転しているだけで、高速で飛び回っている訳ではありません。「1個の水素原子=1個の電子」と解釈しなければ有機化学の物理基礎など語れないのであって、この水素原子を並べて極性を連鎖させると「水素原子電流(生体電流)」が誕生してくる事は承知の通りです。一般で扱う電流とは電子が配列した「電子磁束流」の事ですが、有機物質に流れる電流とは水素原子が配列した「水素磁束流」の事なのです。早い話が、有電荷粒子の軌道運動とはその粒子の化身を作る運動であって、地球磁場圏の中に月磁場が形成されて、地球の生命体は皆月磁場によって育てられたと言っても構わない訳です。当然、衛星の月が地球の生命材料を集めてくれたと言っても過言ではありません。


現代科学は、様々な光学機器を利用した「スペクトル解析」によって物質の成り立ち構造を見定めてきており、原子吸光スペクトル(線スペクトル)や、マイクロ波スペクトルや、赤外線スペクトル(ラマンスペクトル)や、紫外線スペクトルや、核磁気共鳴スペクトルや、質量スペクトルなど、あるいはX線回折や、電子線回折や、中性子線回折などを利用して精密な計測を行なってきました。そのお陰で、今や大半の物質の分子構造が明らかにされているのが現状です。物質は刺激を与えると発光するし、また特定の光を吸収する性質を有する事から、ミクロの世界を覗く為には光学系の機器を発達させる必要があった訳です。銀河民族も最初は光線系の機器を通して物質の組成を解析していましたが、やがて力線系の分析器が開発されると、光学系の機器は大昔の調度品となり、お蔵行きの存在となりました。光系の検査機ではアバウトな構造分析はできるものの、極小のミクロ世界を覗く事ができず、素粒子の形体やその運動など何も見えなかったからです。ちなみに、力線機器では素粒子の渦巻骨格や中心物体の内部まで映像として見る事ができます。
「物質とは何ぞや」を分かった上で述べている言葉と、地球人の科学者の様に単なる憶測や類推だけで述べている言葉には大きな違いがあります。物質世界とは、「要は」運動の世界であって、そこには原理や法則というものが必ず存在しています。物事は原則的に道理に従って発現するもので、その枠枷の域を逸脱した奇想天外な事象が起こる筈もありません。この宇宙とはいわゆるコスモス(秩序)であって、その言葉の背景に理路整然とした哲理があるか否か、具体的に言えば、万物万象をちゃんと説明する事ができるのか否か、そこに本物と偽物の差があります。化学反応と言っても、物と物が一体何の力を介して結合しているのか、つまり水素と酸素がどんな仕組みで結合しているのか、当然我々は分かっていますが、残念ながら地球人は本当の事実を誰も知りません。教科書そのものに「嘘」が書れているからです。素粒子とは何か、原子とは何か、100種の元素とは何か、それらは一体何の力で結合し、複雑な分子構造を奏でているのでしょうか。
水素と酸素、あるいは水素と炭素の化学結合が電子を媒介とした「共有結合」で行われているというのが現代化学の見解ですが、そもそもこの宇宙には特定の粒子を媒介にした結合様式など皆無に存在しません。当然、あらゆる接合子概念、例えば陽子と中性子を接合する中間子仮説も、あるいはクォークとクォークを結びつけるグルーオン仮説も全て架空の産物であって、科学者の詭弁に過ぎません。そんな馬鹿げた仮想粒子をわざわざ想定しなくても、素粒子には元々結合能力が備わっており、素粒子同士は互いの磁極で引き付け合って結合が起こっています。また元素にしても、それぞれが外殻電子の軌道磁界を備えており、軌道磁界が形成する磁極(N極とS極)同士の結合によって化学結合が起こっています。いわゆる磁極結合(NS結合)で全ての化学反応を網羅できるのであって、電子が互いの元素間を行き交いするから結合が起こるという道理も理屈も屁理屈も通らない破茶滅茶な考え方は捨て去るべきだと思います。

昔のブログにも掲載しましたが、「元素の結合手」である「原子価」とは一体何の力なのでしょうか。水素は1価で酸素は2価、炭素は4価で窒素は3価、フッ素は1価でナトリウムも1価であると誰が決めたのか分かりませんが、誠に奇妙な慣習的な定め方です。原子は基本的に最外殻の電子軌道磁界の極性によって結合している理由から、水素原子の軌道磁界の極性(N極とS極)は2個であって、「水素は2価」であると決定しなければなりません。当然、ナトリウム原子もフッ素原子も2価を呈しています。それでないと、水素分子の成り立ちや、水素原子が連鎖したポリ水素の構造や、水分子が連鎖したクラスター構造を一体どうやって説明するのでしょうか。化学は「ファンデルワールス引力」によるものだと説明していますが、それこそ詭弁であって、この宇宙にはニュートン力学が語る様な「物体引力」という「まやかしの力」など存在しておりません。電子の軌道磁界が呈する極性力だけで全ての化学反応を説明する事が可能であって、なぜ考え方を改めないのか、我々には地球人のやる事がさっぱり理解できないというのが正直な感想です。
それと、大きな元素の核子量に間違いがあって、陽子数と中性子数の存在比率が真実の数とは大きく異なります。原子質量の大きな元素の原子核には「無電荷粒子(D-重合体)」が陰電子を抱えた状態で冬眠しており、その質量数を全て中性子数にしてしまっているのが地球科学の現状です。また、「イオン概念」も間違えており、イオン化とは元素自らが起こす行為ではなく水の六員環のなせる技であって、基本的には生体(ヒール)がその元素の無毒化と、運搬用の形体に切り替える現象です。地球の水の操作は全て天体ヒールが行なっています。更に生体内に於ける化学反応は基本的にヒール遺伝子が統括をしており、その命令に従って代謝が行われています。物質同士が勝手に反応しているのではなく、生体内の物質反応には色々と制約がある理由から、身体ヒールが化学反応をコントロールしている訳です。これから有機化学の基礎を学ぶにあたって、科学の既成概念を一度初期化してもらって、新しい学問を学ぶ姿勢で取り組んで欲しいと思います。
② アルカン類
有機物と言えば「炭化水素」だと誰もがそう連想しますが、有機材料は水素(H)、炭素(C)、酸素(O)、窒素(N)という4種類の元素で構成されているのが普通、これらの元素にも「順位」が在って、有機物の本質(陽)を象徴するのが「水素」であり、それに対して有機物の形質(陰)を象徴するのが「炭素」であって、炭素は有機物の基礎骨格を担っています。一方、「酸素」は有機物の作用点や反応点を担う役割であり、また「窒素」とは有機物の立体骨格を担う役割の元素と言えます。有機物の特徴は単位磁場を呈する事であり、水素電流をループ循環させて分子の電磁場を形成しているか、さもなくば環形構造を呈して分子磁場を形成しているか、いずれも物質生命とも表現ができる準生物として振る舞う物質です。水分子(H2O)も有機物の一種と言えますが、材料状態(H2O分子)に意味があるのではなく、これらの分子が連結し、環形(シクロ)を呈する「六員環構造」になって始めて分子磁場を呈する「生きた水」として作用を及ぼす事になります。また、ペントース(五炭糖)もヘキソース(六炭糖)も、あるいはアスコルビン酸(ビタミンC)も環形構造を取らない限り、本来の機能を果たす事が出来ません。
脂肪酸の様なメチル基を連鎖させている長鎖の「飽和化合物(アルカン類)」には一般的に「CnH2n+2」という構造式で表す事ができます。n=1ならばCH4(メタン)、n=2ならばCH3・CH3(エタン)、n=3ならばCh3・CH2・CH3(プロパン)、n=4ならば、CH3・Ch2・CH2・CH3(ブタン)、n=5ならば、CH3・CH2・CH2・CH2・CH3(ペンタン)といった具合に、いくらでも炭素鎖が伸びていきます。ちなみに、n=10ならばデカン、n=20ならばエイコサン、n=30ならばトリアコンタンと言います。アルカン類の炭素鎖に二重結合や三重結合を含む場合は「不飽和化合物(アルケン類)」となり、アルカン類とは異なった化学性質を示しますが、基本的に飽和化合物であるアルカン類は燃焼以外(酸素との結合)には他の物質との化合は極めて起こし難いのが最大の特徴です。その理由とは水素原子の極性に在って、電子の軌道磁界から放たれる「水素磁束(電流)」が分子を循環して「閉塞」しているからだと考えられます(触手が無い)。例えば、水分子(H2O)は触手をオープンにしており、同じ水分子同士と何時でも結合できる状態にありますが、メタン・ガス(CH4)の四つの水素原子は炭素原子と互いの磁束を循環させており、メタン電磁場という固有の場を囲っています。
下記に示したのが、水分子の軌道磁界図とメタン分子の軌道磁界図であり、酸素原子と水素原子が、あるいは炭素原子と水素原子がどの様に磁極結合を起こしているのか、そしてそれぞれの磁束がどの様に動いているのか、それを見比べたものです。化学式を見ただけでも具合が悪くなる人も多いのに、その化学結合を引き起こす電子軌道磁界の構造分析まで突き詰める話には「吐き気」をもよおす方も居るだろうと推察しますが、この部分をしっかり理解して納得してもらわないと宇宙生命論の有機化学を学んだ事にはなりません。最初のA図(水分子)ですが、酸素原子のPxとPy軌道電子(襷型)が描き出す軌道磁界のN極と、水素原子の1s軌道磁界のS極が結合して、その磁束がN極から外界へ放たれていますが、この状態は磁石棒が普通に存在する状況と一緒であり、磁石はいつでも結合できる状態にあります(余力を残している)。しかし、B図(メタン分子)の場合は炭素原子のPxとPy軌道電子(十字型)が描き出す軌道磁界の両極には、それぞれ2個の水素原子を捕獲している理由から、水素原子のN極から噴き出した磁束は反対側の水素原子のS極に吸収されて循環するという閉塞場を呈している事が大きな違いとなります。


本来、水分子も炭素原子と同様に酸素原子が本来4価である理由から、「H4O」という形態を取っても不思議ではないのですが、酸素と水素の親和性が異常に強いことから、酸素が即座に介入して2(H2O)と言う形態を取って落ち着いてしまいます。それに対してメタンは単独分子で居られる訳ですが、圧力が付加されると炭素原子同士が重合して鎖状に連鎖していく傾向が強く、それらが有機物の基礎骨格(炭化水素)を作り上げる事になります。炭素原子は本来十字型の電子軌道を有しますが、4個の水素原子を捕獲すると、水素原子同士の電荷反発によって自然に109度の間隔を開ける様になります。アルカン類の炭化水素(主に石油成分)は分子量が軽いメタン、エタン、プロパン、ブタンまでが常温で気体を呈しますが、ペンタン以上は常温で液体を呈しており、いずれも揮発性が高く、また分子自体に極性を持たないのがその特徴と言えます。n=8や、n=10のオクタンやデカンになると、CH2鎖の水素原子の磁束が横に走って分子表面に水素磁束(電流)が流れて固有の電磁場を囲う理由から、まるで生物体内に存在する生体物質の様に見えます。生体電流を運ぶコリン電線とはCH3が6個直列した単位の羅列であり、それによって不随意電流(自律神経電流)を伝えている事は承知の通りです。
その2に続く
【音声読み上げ】


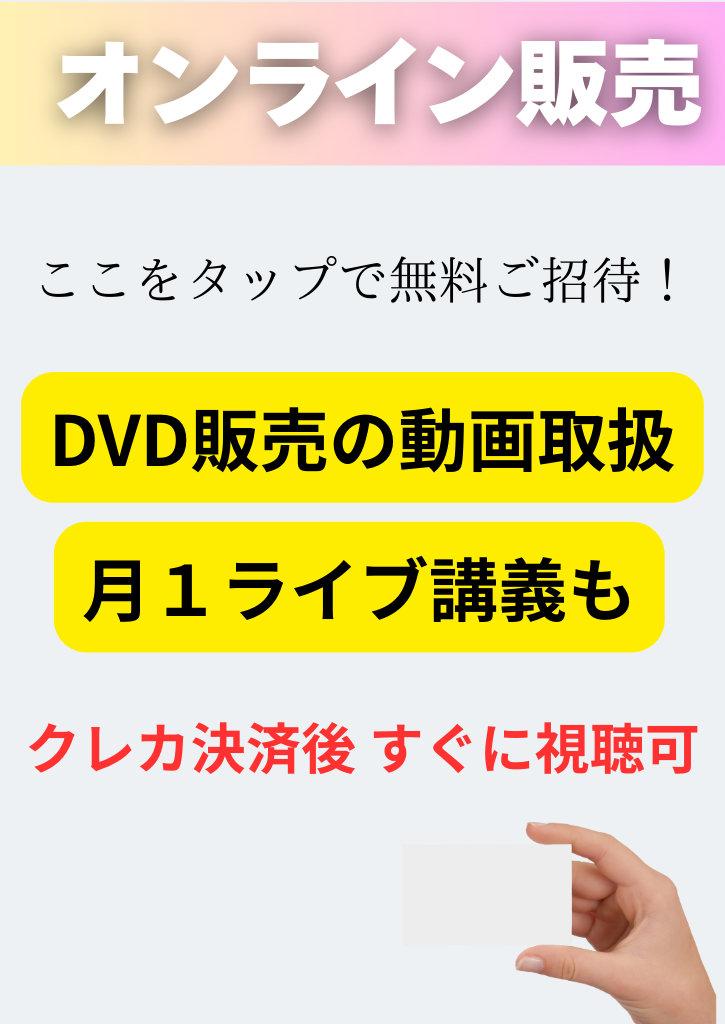





Comments are closed