〈原子核反応の統一理論モデル 4〉
原子核反応の統一理論モデル 4
2) 原子核の系列分類
我々が学校の授業で習った元素分類(メンデレーエフの周期率表)は原子の電子軌道分類であり、それは軌道電子が生み出す電磁場の化学性質の傾向を示すもので、原子核の性質を示すものではない。諸元素の原子核はその崩壊系列に基づいて系統立てた分類が可能であり、個々の原子核の諸性質が統計的に厳格に定められている。この分類法は原子核が所有する核反応能力や原子の進化、および原子核構造にも関係してくるので、ここではそれを簡単に説明しようと思う。
炭素原子の原子核がどの様な構造に成っているのかと聞かれても、残念ながら今の科学ではそれを正確に答える事は出来ない。多分、6個の陽子と6個の中性子がゴチャ混ぜになって固まっており、丸い形を呈していると誰もが推測するだろう。だが、実際の炭素原子核はその想像とは異なり、三つのHe単位が▲型に配列した中抜きのコアレス構造をしていると言ったら貴方は私を笑うだろうか? もし、貴方に私を笑うだけの自信があるなら、炭素原子核の本当の構造を物理的に納得の行く説明を付けて私に呈示して欲しいものである。
炭素原子は元々断裂した3組のヘリウム・チェーンがその両端を結合して固まったものであり、その形は当然三角形の帯状を呈している。そのヘリウム・チェーンの中を交互に核子の中心磁束が回転しており、右巻きと左巻きに磁束が回転している為に、検出不能な特殊な核磁場(零磁場)を形成している。核磁場の中心点には中心回転体の存在は無いが、三角形の中心点に核磁場の重力が集中している。つまり、3組のHe単位は原子核の赤道ベルトを成しているのである。当然、炭素原子核が中性子を捕獲すれば、その中性子は核磁場の中心回転体となって中心部に居座る事になる。中性子を吸収した炭素13は中性子のスピン量と等しい1/2 spinを呈する核異性体である。承知の様に、炭素12はヘリウム単位から構成されており、スピンは相殺されて、全体回転(核スピン)はしていない。
図 15 (炭素原子核と窒素原子核の構造比較)
原子核が三角形を呈しているのは炭素原子だけではない。窒素原子も同じ三角形を呈している。3組のHe単位と1組のD単位からなる核子チェーンが一塊に成ったものが窒素原子であり、三角構造が定まると余剰のD単位は核磁場の中心点に移動し中心回転体となる。と言うより、D単位を中心にして丸まったと表現した方が早い。当然、核磁場の中心点にはデュートロンが存在する為に、窒素原子核の核スピンはそれと同じ1spinを呈示している。窒素原子は炭素13と同じく中心回転体を所有しているので、その回転体の中心磁束が外に吹き出し零磁場を包み込む為に、検知が可能な一般の核磁場を持つ事になる。
この様に、原子核が長鎖のヘリウム・チェーンが細かく断裂して誕生してきたものと考え、またHe単位の基本構造を主眼として考えれば、見た事も無い原子核構造の真実の姿を正確に洞察する事が可能である。全ての原子核の陽子と中性子の存在比はほぼ均等であって、片方が2個も3個も多いなどという事は有り得なく、また仮に多くても、中性子放出やβ崩壊を引き起こして原子核は常に安定した形態を整える性質を持っている。我々が想像している以上に原子核構造の解明は意外と簡単であると言えよう。
ここで以前、我々が学んだ放射能元素の四つの崩壊系列を思い出して頂きたい。不思議な事に、全ての放射能元素は例外なくこの四つの崩壊系列に帰属し、定められた崩壊系を辿って分解してくる。四つの崩壊系列とは、母元素をトリウム(Th232)にしたTh崩壊系列(4n+4)と、ウラン(U235)から派生するAc崩壊系列(4n+3)と、ウラン(U238)から派生するU崩壊系列(4n+2)と、ネプツニウム(Np237)から派生するNp崩壊系列(4n+1)の四つの事である。これらの崩壊系列の核子数が単純な数理で表現できるのは一体なぜなのだろうか? そして4nとは一体何を意味しているのだろうか?
ところで、この四つの崩壊系列はそれぞれ鉛やビスマスで終わってしまうが、この崩壊系列はそれ以下の元素には通用しないものなのだろうか。一般の安定元素は放射能元素の様な素早い核崩壊(特にα崩壊)を起さないが、極めて緩やかに核崩壊の行程(特に中性子崩壊)を辿っており、下位の元素へと遷移している。しかも原子核が一様にHe単位から構成されているのであれば、この四つの系列崩壊は全元素に通用するものであって、放射能元素だけにしか通用しないものではあるまい。
例えば、原子量が12の炭素原子核は(4n+4)で表されるTh崩壊系列の元素であり、また原子量が14の窒素原子核は(4n+2)で表されるU崩壊系列の元素であって、これらには系列単位の共通性質と特徴が統計的に備わっているのである。素粒子物理学には全ての粒子をボーズ粒子とフェルミ粒子に分ける意味のない物理統計学が存在するが、そんな高慢な統計学を企てるのは少々時期尚早であって、それ以前にもっと基礎的な元素の統計学を完成させておくべきではなかったかと思われる。この原子質量統計は完成していなかった為に我々が完成させたが、特に無電荷粒子を包含する新しい元素概念を構築する為には必要べからざるものと思われる。
この系列分類法の使い方は決して難しいものではない。例えば、鉄(Fe56)は4で割り切れる原子量なので、魔法数原子核と呼ばれる極めて安定したTh崩壊系列(4n+4)の元素であり、原始的な初期形態の元素である事が分かる。当然、全てD単位の無いヘリウム単位から構成されているので、核スピンの無い(核磁場が無い)元素である事も分かる。原子量が56なのに対して原子番号は26という事は、56 − 26×2 = 4で、4個の余りを持つという事は、鉄原子が1組の無電荷He単位(2組の無電荷D単位)を所有している事になる。つまり、これはFe56原子核が不安定な状態に陥ると、最低2回のβ− 崩壊を起こす潜在能力を持っている事を意味しているのである。
一方、鉄(Fe57)は4で割ると端数1を持つNp崩壊系列(4n+1)の元素であり、鉄(Fe56)とは異なる原子核特性を持つ元素である。鉄(Fe55)程の活性力は無いものの、核スピンと核磁場を有する奇数系列元素であって、高い核反応力を持っている。当然、余剰の中性子を1個持っているので核スピンは1/2だが、X線励起すると中心回転体が変成されて3/2 spinを持つ核異性体へと転移する。Fe57は本人が望んでなくても、いずれは中性子崩壊を起こして安定したFe56に遷移する運命を持った原子と言える。
Fe57の無電荷粒子はFe56と同じく2個の無電荷D単位を持っているので、合計2回の自己修復作業(β− 崩壊)を起こす能力を備えている。もし何かの外部作用でFe57の一つのヘリウム単位が外に飛び出したら、Cr53-Mn53-Fe53 と2回のβ− 崩壊を引き起こし、電荷の補正をして元の自分の姿に戻ろうとする。しかし、一時的には戻れるものの、53の原子量で26の電荷量は許容限界を超えており、今度は逆にEC反応を引き起こして無電荷粒子対を形成し、結局Cr53で落ち着いてしまう。ちなみに、Fe57もCr53もMn53もFe53も同じNp系列元素である。一般に、α崩壊やβ崩壊では系列は変化しないが、中性子崩壊の場合は系列自体が変化してしまう。では、原子核の四つの崩壊系列の一般的性質について具体的に説明したいと思う。
✤ Th崩壊系列元素の特徴
この系列元素は母元素のトリウム(Th232)から崩壊派生してくる一群の元素であり、その原子量は(4n+4)で表される。簡単に言えば、一連の長さのhelium chainのうち、端数(余り)を持たない元素の一群である。従って、この系列元素は純粋なHe単位の塊であり、元素本来の基本形態と言える。この系列の一番小さな元素はヘリウムである。
この系列元素の最大の特徴は、構造的に極めて安定した原子核を有するという事である。承知の様に、4の倍数(12、16、20、24、28、32など)は魔法数と呼ばれる数であり、これらの原子量を持った原子核は極めて安定している。電子軌道は原子核構造を基本にして組み立てられているので、当然この魔法数に適った電子軌道が組み立てられる為に、化学的にも比較的安定した元素が多い。無論、化学的に安定という意味は“不活性”という意味である。原子核が安定していれば、元素の種類や産出量が多いのは当り前であって、四系列の中では最も物量が多い。この系列は偶数族元素(陰族元素)の象徴的な存在と言える。また、この系列はその不活性さから不活性ガス系列と呼ばれている。
系列元素の種類は、 He4、Ne20、Ar40、Kr84、Xe132などの希ガス族元素の他に、C12、O16、Mg24、Si28、S32、Ca40、Ti48、Cr52、Fe56、Zn64、Se80、Sr88などが有名であり、その他全ての偶数族元素の核異性体に必ず存在している。これらの元素は酸素という特別な例外を除けば、比較的不活性な元素が多く、自然界に単体で存在する物も多い。また物質の骨格や物の組成の基盤になる元素が多く、如何にも母体的な(原始的な)匂いを放つ一群と言える。酸素はケイ素と結合して岩石の主成分になるばかりか、水素と結合して水となり、有機物の素材としては絶対に欠かせない土台的な元素である。
この系列の安定性は放射能元素でも同じである。ちなみに、Th232の核崩壊の半減期は 1.405 × 1010 年であり、四系列の母元素の中では一番長い。計測した全元素の中で一番核反応が遅いものはNd144やSm148の核崩壊である。Sm148のα崩壊の半減期は何と7 × 1015年であり、これらの元素はいずれもTh系列の元素である。基盤や土台となる元素が簡単に崩壊したり、軽はずみな化学反応を起こしてもらっては困るのである。
一般に、Th系列元素には核スピンに由来する核磁場の存在が無く、核内に秘められたエネルギー量(気密度)は比較的少ない。その為、内部気圧の高騰によって吹き出すα粒子の放出が少なく、自発的な核反応を滅多に起こさないのが特徴である。その原子核スピンは原則的に零(0)であるが、奇数族元素の核異性体でTh系列の物は、例外的に整数倍(1、2、3、4)のスピンを持つ。原子核の安定性は半減期の長さにも比例するが、天然に現存する放射能元素の中で自発的な核分裂性を持たないのは、この系列元素だけである。
✤ Ac崩壊系列元素の特徴
この系列元素は母元素のウラン(U235)から崩壊派生してくる一群の元素であり、アクチニウムの名はこの系列上に派生するAc227に由来している。その原子量は(4n+3)で表されるが、簡単に言えば一連の長さのhelium chain のうち3/4 He単位の端数(余り)を持つ元素の一群の意味である。この系列の一番小さな元素はトリチウムとヘリウム3である。Ac系列はその名に相応しく大変アクティブな系列であり、核反応も盛んであれば、また化学反応も盛んな元素が多い。Th系列を偶数族元素の母親的な存在とすれば、Ac系列は奇数族元素の父親的な存在であり、種類や物量ともにNp系列を圧倒している。この系列の最大の特徴は、過激なまでのその反応力であって、別名はハロゲン系列と呼ばれるが、自発性の核分裂性を持つ為に核爆弾系列とも呼ばれている。
系列元素の種類には、F19、Cl35、Br79、I127などのハロゲン族元素の他、 有名なものではLi7、Na23、Al27、P31、K39、V51、Mn55、Co59、Cu63、 As75、Rh103、Ag107、In115、La139、Tb159など、大変有益性に優れ、攻撃力と反応力に富んだ男性的な元素が多く、種類が最も多いのも特徴の一つである。Th系列元素が基盤的な役割を担う不活性で植物的な元素が多いのに対して、対照的にAc系列元素は作用力を直接行使する活動性に優れた動物的な元素が多い。
また、この系列元素は原子核の安定を求めて好んで中性子を吸収し、Th系列に戻ろうとする傾向が強いが、自然の潮流に反する行為は結局自らの原子核を不安定にしてしまう。U235やPu239は喜んで中性子を吸収するが、その結果が核分裂連鎖反応を招いてしまう。Ac系列は逆に粒子を放出してU系列元素に遷移するのが無理のない方向である。
この系列元素は核スピンに伴う強い核磁場を呈示するので、核内に膨大な量の気をプールしている。原子核は強固だが、反面脆(もろ)くて壊れ易く、また気密度の圧力が高じ易く、定期的なガス抜き(α崩壊)が必要であるが、なぜか一度に全部吐いてしまう傾向が強い(核分裂)。核スピンは本来、1/2 と3/2 であるが、多くの場合はHe単位と重合し、重陽子チェーンの様な中心回転体を形成している。その為、5/2、 7/2、 9/2 spinという強烈な回転を有する元素が多く、その分、核磁場に馬力がある。活性力が高いという事は優れた作用能力を発揮出来るという事だが、生体の様な調和を必要とする組織には、ハロゲン族の元素は薬よりもむしろ毒になるケースが多い。U235の有効性は原子力発電でもお馴染みだが、同時に核爆発と放射能という悪魔の側面は避けられようもない。
✤ U崩壊系列元素の特徴
このウラニウム系列は母元素のU238から崩壊派生してくる一群の元素の総称名であり、その原子量は(4n+2)で表される。つまり、一連の長さのhelium chainのうち、2/4 He単位の端数を持つ元素の意味である。この系列元素で一番小さな元素は重水素原子である。当然、U238は59組のHe単位と1組のD単位から構成される巨大原子核を持っている事になる。総陽子数(actron)と総中性子数(neutron)の数は一緒で、ともに119個であり、13組の無電荷He単位と1組の無電荷D単位を持っている。
この系列はTh系列と同じ偶数族の元素であるが、元素の種類と存在量は僅かでありTh系列に圧倒されている。人間に例えれば、現役バリバリの母親と、その影に隠れたもの静かな娘といった感が深く、直ぐお嫁に行って姿を消してしまう過渡的な元素の一群と言えるかもしれない。原子核の安定感を誇る偶数族元素とは思われ難き不安定な元素が多く、中性子を放出して次のNp系列元素へと遷移する運命にある。
この系列の主な元素は、D2、N14、Ni58、Ge74、Zr90、Mo98、Cd114、Te130、Ba138、U238などが有名だが、他に偶数族元素の中に同位体として微量に存在する。いずれの元素も不活性な元素であり、それ自体では効果的な作用を及ぼす事は無いが、他の系列元素と化合するか、あるいは中性子を吸収して系列を変化させれば際立つ効力を呈示してくる。
例えば、窒素原子はそれ自体不活性ガスであるが、酸素や水素と化合する事によって、ニトロ基やアニル基となって重要な役割を果す事になる。また、U238はそれ自体核分裂性は無いが、中性子を吸収させると核反応を起して核分裂性を持つPu239へと遷移する。そして、重水素原子はそれ自体では物の役には立たないが、互いに重合して集団になる事によって最も重要な役割を果す。まるで加工用の材料とも思える元素の一群がこの系列の特徴である。その様な意味では、若い娘さんは早く結婚してペアーを組むか、あるいは男性化して(中性子を吸って)バリバリ仕事をするか、さもなければ女性の大集団の一員となるか、そのいずれかを選択すべきかもしれない。
この系列の原子核スピンは本来1であるが、他のHe単位と合体して一本軸の中心回転体を作り上げる為に、整数倍(0、1、2、3、4、5)のスピンを呈する場合が多い。ちなみに、N14の核スピンは1であり、その中心回転体がスピン量1を持つD単位である事が推測出来るが、Ni58のスピン量は0であって、中心回転体が二本軸で構成され、互いのスピン量が相殺されている事が分かる。だが、同系列元素のCo58のスピン量は2であり、それは中心回転体が1本軸のHe単位で構成されている事を暗示している。無論、Co58は不安定な人工核種であって、EC反応を引き起こして、僅か70日余りの半減期で安定なNi58へと遷移してしまう。
✤ Np崩壊系列元素の特徴
ネプツニウム系列とは母元素のNp237から崩壊派生してくる一群の元素の総称名であり、その原子量は(4n+1)で表される。いわゆるHe単位以外に端数1 (1/4 He単位)を余分に持つ元素であって、その一番小さな元素は水素である。この系列は主にU系列元素の中性子崩壊で誕生してくる。当然、Th系列が中性子を吸収してもこの系列になるが、それは逆行程であって一時的なものに過ぎなく、結局は中性子を放ってTh系列に戻ってしまう。Np系列はいずれ中性子を放ってTh系列へ遷移していくという運命の潮流に従っている。それは重水素原子が中性子を失って水素原子になる運命と全く一緒である。
この系列元素は、奇数族の元素とは思い難い反応性に乏しいネガティブな性質をしており、Ac系列元素とはまるで対照的であって、両者の間には華やかなホワイト・カラーのエリート族と、工場に従事する職人気質のブルー・カラー族ぐらいの違いがある。無論、それ自身に社会的な価値や能力が無い訳ではないが、孤独無縁な孤高の元素が多く、社会で皆と一緒に活動するよりも、自分一人で好きな様にやっていきたいという律儀な硬骨漢、いわゆる“大工の棟梁”的な元素が多い。この自己中心的な気質が、大人に成長する以前の青年気質なのか、それとも反対に老人気質なのか良く分からないが、いずれにしても我を失わず、最後の砦を守るが如く片意地を張って突っ張る所はさすがに最終系列の元素と言える。水素原子が踏ん張って崩壊しないから物質が存続出来る事は言うまでもないが、攻撃力や反応力よりも保守に徹した元素が多いのが最大の特徴である。
この系列の有名な元素は、H1、Be9、Sc45、Ga69、Y89、Nb93、Sb121、Cs133、Pr141、Ho165、Tm169、Au197、Tl205などであるが、水素という特別な例外を除けば、いずれもそれ自身の能力は高いが他と協調し合わない孤高な元素が多い。その為、希少価値の系列とも呼ばれている。金やセシウムあるいはツリウムなどはその典型と言える。無論、水素も喜んで酸素や炭素やハロゲンと化合している訳ではない。母親(Th系列)と父親(Ac系列)には逆らえないだけの話に過ぎない。
奇数族元素であるNp系列には必ず核スピンが存在し核磁場が備わっている。従って、核内の気密度は高く、比較的α崩壊を起こしやすい傾向にある。四系列の中ではこのNp系列の放射能元素が一番早い速度で崩壊行程を歩む。いくら片意地を張っても自然界の大潮流には勝てないのである。原子核スピンは陽子や中性子と同じく本来は1/2を呈示するが、その多くは複合的な回転軸を持つ為に、半整数倍(3/2、5/2、7/2、9/2)のスピンを呈示する。ちなみに、Be9は3/2、Sc45は7/2、Y89は1/2 である。当然、Sc45が7/2のスピン量を持つという事は、中心回転体の一本軸の中に7個の核子が存在するという意味になる。
3) α崩壊の謎
元素は皆一定質量を上回ると放射能元素になる。というより、元素はある一定質量まで分解してくると放射線を出さない安定元素となると表現した方が正しいかもしれない。ところで、α崩壊はなぜ周期的に起こるのだろうか。いや、それよりも放射線とは一体何なのだろうか。ここではそんな根本的な話をしようと思う。
そもそも放射線とは原子が放つものではなく、原子核の中から放射されるもので、その種類とは、気の直進流(direct force)、高速のα粒子(helium nucleus)、高速のβ線(electron or positron)、γ線、 X線他の電磁波などである。原子核の中から放射される高密度の「気の直進流」の中にはニュートリノが混ざっているが、それは気の粒の四分子体であり、気の粒の一種であって特別なものではない。無論、その中には空間のどこにでも存在する無電荷のπ-電子対も存在している。
では、原子核はなぜその様な放射線を定期的に放つのだろうか。それを語る為には原子核の構造とそれが形成する核磁場の話をしなければならない。先ず巨大元素の原子核構造から簡単に説明すると、原子核は環状に取り巻くHe単位の複数の帯から構成されている。その姿は一見すると収縮したゼンマイの様な渦構造に良く似ているが、正確に言えば渦ではなく、ループした帯の集合体である。その平面構造の中心点に垂直に立つ回転体が存在し、それが核スピンと核磁場を生み出している当体である。
しかし、核磁場には検出可能な通常の磁場と、検出不能な「零磁場」の2種類があって、この二つの核磁場が原子核を支えている。原子核の構造を基本的に支えて維持しているのが帯状単位の生み出す「零磁場」であり、その上から原子核全体を包み込んでいるのが中心軸の回転体が生み出す通常の「核磁場」である。「零磁場」の仕事は原子核本体を機械的に維持し、気の漏れない完璧なシールド磁界を作る事である。無論、その磁界はHe単位の中を交互に貫通する超伝導磁束の角運動から生まれる超伝導磁界である。現在の科学には原子核構造はもとより、残念ながらこの「零磁場」の概念自体が存在しない。
原子核の統括意識を司り、その全体的な作用を制御しているのが中心回転体の磁束が形成する核磁場である。その磁気の質は地磁気と同じものであり、検出は可能である。中心回転体の磁束は原子核直径を遥かに超える遠方領域に及び、最内殻の電子軌道にまで到っている。だが、核スピンの無い原子核には核磁場は存在せず、あるのは帯状単位が生み出す零磁場の超伝導磁界のみである。
図 16 (巨大原子核の構造図)
さて、ウラン原子を外側から覗くと、92個もの大量の外殻電子が生み出す軌道磁界によって、玉ねぎの皮の様に幾重にも包まれた状態である。原子核はその電子雲の奥底に小さくポツンと佇(たたず)んでいるという状態である。電子の軌道磁界は大小46層にも及び、その全ての磁界が磁場重力を生み出し、原子核を圧縮している。軌道磁界よって捕獲された気の粒は原子核内にプールされ、零磁場の超伝導磁界の中に高密度状態で閉じ込められている。当然、時間が経過すればする程、原子核の内圧が高じてくる事は述べるまでもない。
一方、完全密封を信条とする零磁場の超伝導磁界はたった1個の気の粒も漏らさない完璧なシールド能力を備えているが、弱点が全く無い訳ではない。それは構造上の問題であって、帯状にサークルするHe単位、つまり超伝導磁束を生み出す本体そのものに弱点があり、磁界の土台に当たる赤道部が軟弱な為に、自己の内圧に耐え切れなくなるという事態を招く。平たい表現を使えば、高い内圧に耐え切れず、土管の蓋(ふた)が吹き飛ぶという事態が発生するのである。つまり土管の蓋とはHe単位の事であって、ヘリウム原子核が吹き飛ぶのである。無論、それがα線の正体に他ならない。
原子核は自己の内圧が高じてくると、核爆発を恐れる余りに非常手段としてHe単位を放出し、定期的に「ガス抜き」を行わざるを得ない。これは一種の減圧作業であるが、この作業は原子核でなくても、銀河系や太陽系、そして地球系という渦磁場でも起こる自然界では別に珍しくない当り前の作業と言える。原子核の場合はその傷口を修繕し、失った電荷を調整して原子核構造を再び組み直すという作業が引き続き行われる為に、少々複雑な核反応行程を経由するが、渦磁場のガス抜き作業に補修作業は要らない。当然、陽子や電子という小さな渦磁場でもガス抜き作業は起こっている。
U崩壊系列のウラン(U238)は核スピンと核磁場を持たない元素である。一方、Ac崩壊系列のウラン(U235)は7/2スピンを持つ強い核磁場を有する元素である。両者は同じウランの同位体元素であるが、根本的な違いがある。高速の中性子線を互いの原子核に打ち込むと、前者は滅多に爆発しないが、後者は必ず爆発する。しかも、一度爆発すると周囲の原子核を次々と誘爆させていくという核分裂連鎖反応性を示す。核磁場を持つU235はそれを持たないU238と比較してなぜ爆発し易いのだろうか。無論、その答えは核磁場がある分内圧が高じ易く、更にガス抜きが難しくなるのがその理由である。
銀河系がまだ若く馬力のある吸核渦の時代、その渦磁場の中心部には膨大な量の気がプールされていたと思われる。しかし、渦流の回転速度が落ち始めて重力が減退すると、内圧に負けて高密度の気の直進流が吹き出し、今の重力の強さに相応する内部圧に調整されたと考えられる。その吹き出した気の直進流が小さな渦の群れを発生させて一群の星を誕生させたのが、小さく幼弱な星を抱える現在の「散光星団」6) であると思われる。また、そこに在る巨大な水素ガスの雲柱こそ気の直進流の姿と言える。それと全く同じ事は太陽系にもあって、吹き出した気の直進流が生み出した物が奇妙な公転軌道を取る大量の彗星群と思われる。
この様な渦磁場の大規模なガス抜きでなくても、太陽や地球は定期的にガス抜きを行っており、太陽のフレアー爆発や地球の火山爆発も単なるガス抜き作業に過ぎない。それは放射能元素のガス抜き作業(α崩壊)と何も変わるものではない。
α線が放出されると、それに伴って気の直進流が吹き出し、その際の原子核振動が陽子を揺すってγ線やX線を放出させる原因となる。陽子(actron)が激しく振動すれば、それ自体がX線を放つばかりか、内軌道を周回する反電子が振動して、陽子の中からγ線が放出される。また、α線の放出直後に原子核の中から電子線が放出されるのは修繕作業の核反応(β崩壊)によるものであって、飛び出したその高速電子とは、無電荷ユニットが内蔵する電子であり軌道電子ではない。この様な考え方をすると、放射線の全ての謎が明確に解ける。
4) 零磁場と何か
零磁場とは一体何の事だろうか。聞き慣れない言葉だと思われるが、大変重要な意味を持つので、それについて少し説明しておこうと思う。ヘリウム・チェーンは磁極の方向が異なる2本のデュートロン・チェーンが重合して出来たものであって、その中には互いに反対の方向に走る核子磁束が流れている。ヘリウム・チェーンがそのままの状態であれば別に問題は無いが、その端と端が結合して環状にループすると厄介な問題が生じてくる。核子の中心磁束が角運動するのだから、当然反作用ベクトルの三角形運動が起こり、そこには力の場が形成されている筈である。だが、逆回転するもう一つの中心磁束も同じ三角形運動を起こす為に、磁場が相殺し合って一見何も無い様に見える。それが俗に言う所の検出不能の零磁場状態である。
我々はファラデーの電磁誘導の原理を学び、それから発電機やモーターを発明して実際に利用している。彼によると、電磁場の中心磁束が互いに打ち消し合うと磁界が消滅して電流が流れない事になるが、磁束が打ち消し合う現象など本当に存在するものだろうか。それは互いの磁束が衝突し合って均衡状態になる意味であって、本当に消滅している訳ではない。陰電子と陽電子が結合して互いの電荷が相殺されるという意味は、電荷がどっちつかずの均衡状態になる為に、一見無い様に見えるという話に過ぎなく、別れれば互いの電荷が出現してくるものである。それはスピンの相殺も全く同じ事であって、プラスとマイナスで互いに零になるという発想は数学がもたらした最悪の概念と言えよう。
図 17 (零磁場の三角形運動)
さて、ループしたサークル状のヘリウム・チェーンは図に示す様な正八面体の力の場を形成する。当然、核子磁束が回転している為に、実際は八面体ではなく球体状を呈しているが、一見すれば何の変哲もない普通の球体磁界に見える。しかし良く見ると、それらはダブル・ピラミッド構造を呈しており、それぞれの磁束が形成した独立した二つの四角錐から成り立っている。つまり、一つの磁界に二つのN極が存在する磁界なのである。この大変奇妙な形態の力の場を我々は零磁場と称している。
普通、1本の核子磁束の角運動で同じ形の磁界が形成されるが、その場合は力の三角形運動が北半球と南半球を一挙に描いて、球体磁界全体の基盤フレームを創り上げる。当然、N極から吹き出した力はS極を経由してその中心点に戻っており、出口と入口に当たる二つの磁極が形成されている。これらのN極とS極を切り離す事は不可能であるが、しかし磁極といっても所詮ただの出口と入口という区節点に過ぎず、力の通り道を強制的に変えてやれば、それらは別の場所に移動せざるを得ない。
分かり易く表現すれば、磁束が角運動を起こすと、その反作用ベクトルは馬鹿の一つ覚えの様に決まり切ったパターンで三角形運動を起こし、正八面体の力の場を形成する。その反作用ベクトルの正確な運動パターンが分かれば、それを操作する事も可能だという話である。例えば、南半球を作らずに北半球のみを作らせたいなら、反作用ベクトルを北半球の中でのみ循環させれば良い訳である。つまり、正八面体運動ではなくピラミッド(正四角錐)運動を起こさせれば、北半球だけの力の場を作る事が出来るのである。
これは「三角バイパス法(triangle bypass)」と呼ばれる磁場の操作術の事であるが、この方法を利用して宇宙船(円盤)の永久推進力を生み出す事が出来る。地球上でこの技術を知る者は誰もいないが、宇宙人なら誰でも知っている常識的な技術と言える。なぜなら、この方法を知らなければ円盤など絶対に造れないからである。もし、貴方がその技術を欲しいなら、立派な生きた設計図を参考にされたい。一体誰がそれを建立したのかは知らないが、そのお手本とはエジプトのギザのピラミッドの事に他ならない。それを単なる王家の墓だと信じている歴史学者が多い様だが、その本当の意味と価値に気が付かないならば、まさに地球人にとっては「豚に真珠」のピラミッドと言えよう。そもそもピラミッドとは地球人が啓示を受けて建立したもので、元々地球人の設計によるものではない。
さて、話を本論に戻そう。向きの異なる2本の核子磁束の角運動は、それぞれの反作用ベクトルが躍動して力の場を互いに形成しようとするが、三角形の二行程を描いた次点で相手のベクトル・フォースと赤道部で衝突する。そこでベクトル・フォースは方向を変えて赤道点から直接中心点へと向かって進み、そこから再びN極へ向かうという小循環運動(小三角形運動)を始める。ベクトル・フォースは4本あるので、それらが描き出す全体像は正四角錐であり、回転すれば半球を呈示するものである。この様な運動を全体的に反作用ベクトルの正四角錐運動またはピラミッド運動と呼んでいる。
このピラミッド運動が赤道を挟んで北半球と南半球で行われ、全体として一つの球体磁界が創造される。それが零磁場のメカニカルな構造である。零磁場の特徴は赤道部のhelium chainを境に異なる質の二つの半球磁界から構成されている事であり、二つのN極を有しているという事である。それがなぜ検出不能かと言えば、北半球が左回転しているのに対して南半球が右回転しているからであって、回転磁場の回転が相殺されて、それ自身が一見、回転が無い様に見えるからである。つまり、我々の宇宙は左巻きの陽磁場の世界であり、左に回転する物(αspin)は正の磁場となり、また右に回転する物(βspin)は反対の負の磁場と認識される世界である。一つの球体磁界の北半球が正磁場で、南半球が負磁場を呈すれば、電子と反電子が結合しているのと同じ意味になるのである。
ところで、零磁場だからといってS極が無い訳ではない。磁場の定義では中心磁束(ダイポール磁束)の両端が磁極になるので、零磁場のS極は互いの中心点に存在している。いくら右巻きと左巻きの異なる磁界といっても、中心磁束は中心磁束であり、両者の反撥は避けられない問題である。従って、その磁荷反撥の為に赤道ベルトであるヘリウム・チェーンはその中央から分離寸前な状態にいつも置かれている。その隙間からプールしている気が流出するのは構造上避けられない問題と言えよう。
その様なガス抜きが自然に出来る元素なら良いが、強い核磁場を持つ元素や圧倒的多数の軌道磁界を持つ元素は零磁場が圧縮されて漏れが無い状態に置かれている。そうして内圧が高じてくると、結局は赤道ベルトの蓋を吹き飛ばしてエネルギーが放出される事になるのである。零磁場の赤道部に弱点があるという意味を分かって頂けただろうか。
超伝導磁界の中心点に鉄棒を置くと、その鉄棒は中心磁束に沿って垂直に立ち上がる。別に超伝導磁界でなくても、この現象は回転磁場(重力磁場)なら何でも同じだが、面白い現象だと言えば面白いかもしれない。今ここに三つのHe単位と一つのD単位がつながった原子量が14のヘリウム・チェーンが存在し、それが丸まって端と端が結合したと考えてみよう。当然、半端のD単位を中心にHe単位が丸まる事は予測されるし、またHe単位が三角形に結合した状態でも、その核子磁束は回転を始めて零磁場が形成される事は予想される。
零磁場が形成されると、端数のD単位は零磁場の中心に垂直に固定される。もしその北半球が左巻きで南半球が右巻きなら、D単位は陽子を北に、そして中性子を南にして立つ事になるだろう。その次点でD単位(横結合状態)は既にデュートロン(縦結合状態)に変化しており、それはHe単位の三角形の中心点にデュートロンが垂直に立っている姿だと予想される。陽子(actron)と陰電荷中性子(intron)が結合したデュートロンは当然、それ自身が元々スピン回転量1を持つ物体であり、零磁場の中心点でスピンを始める。もちろん、He単位は回転せずそのまま静止している。この次点で、回転している者はデュートロンとHe単位の核子磁束のみであると考えられる。
中心回転体であるデュートロンは核子磁束を吹き上げて、He単位の三角形をそっくり包み込む核磁場を形成する。その核磁場は回転しており、陽子と同じ左回転の陽磁場であって、地球の地磁気と全く同じものである。外磁場が回転し始めれば、それに従ってHe単位全体も回転を始めて、原子核は全体スピンを持つ事になる。当然、そのスピン量はデュートロンと同じく1である。やがて、全ての中性子(intron)が電子を外界へ放って軌道周回させると、単なるHe単位の塊に過ぎない物体が作用や反応を起こす能力を持った生命体(原子)へと進化し、「窒素原子」が誕生してくる。当然、窒素は端数2を持つU崩壊系列の元素であり、核スピン1を備えた磁気双極子モーメントがプラス(左回転)の元素である。
原子が一体どの様に形成されたのか、その原子核構造はどんな形態なのか、核スピンが何から生まれて、核磁場がなぜ存在するのか、従来の原子概念とは全く異なる新しい物質概念を述べてきたが、この理論を信用するか否かは別問題として、我々は今一度、我々が学んできた学問を改めて見直さなければならないだろう。
5) 三角形運動と未来技術
ここで、本誌によく掲載されるTT.Brown の「三角カイトtriangle kite」の話をしようと思う。三角カイトとは高圧電流(30kV)によって空中浮上する軽素材(aluminum foilとBalsa woodのフレームから構成される)の推進器(vehicle propulsion)の事であるが、その浮上推進力の原理、いわゆる“biefeld-Brown effect”の解明を角運動原理から説明してみよう。重力に逆らって浮上する三角カイトの推進力について、多くの科学者は非対称蓄電作用(asymmetric capacitance)によるイオン風(ionic wind)やプラズマ効果を原因に上げているが、我々はそうは考えていない。
図 18 (写真: 三角カイト)
我々の解答を簡単に述べれば、直流電流の角運動による力の場(電界)の発生が反重力の根本原因である。電線を四角形や三角形に巻いても、その中を走る電流が中心点に対する角運動の形式であれば、その四つもしくは三つの角から反作用ベクトルが中心点に向心して立体的な電界(電磁場)が発生する。当然、その原形は四角形の場合は八面体、三角形の場合は六面体という形状の力の場が形成される。
電界でも磁界でも、あるいは超伝導磁界でも、磁界は全て同じ磁界に対する斥力を備えており、重力という巨大磁場の磁力線に対する反撥作用(シールド作用)を備えている。もし、蜘蛛の糸の様に軽い電線があって、それを三角カイトのアルミホイルの代わりに帯状に巻きつければ、そこには同様な電界が形成されて、全く同じ現象が起こるだろう。もし、三角カイトの浮上力がイオン風やプラズマ効果が原因であるならば、なぜそれは交流では起こらないのだろうか。直流でなければ絶対に起こらない、その理由を追求しなければならない。
三角カイトのアルミホイルを全体的に磁化して、そこに大量の電子バイパスを発生させる為には大電圧が必要である。その電圧流(大電流)はアルミホイルを磁化して電子バイパスを形成させるが、一方、その電子バイパスから繰り出される無数の電子磁束(チビ電流)が角運動を起こし、電界を形成すると考えられる。その証拠に、浮上した三角カイトをバーナーで温めてやると、電子バイパスが崩れて磁界が失せ、それは急激に落下する事になるが、反対に液体窒素で充分に冷却したそれは、電流が増加した分浮上力を増す。無論、電流が増加すれば多大なジュール熱が発生し、特に角の部分から焼き切れてしまうのは致し方も無い。
イオンやプラズマの作用でない事は真空状態で実験すれば簡単に分かる事だが、今の運動力学や電磁気学の理論ベースではその謎を解くのは大変に難しい。特に電流概念が確定していない状態であれば尚更であり、謎解きが出来ないのは仕方が無いと言えば仕方が無い事かもしれない。
さて最後に、読者の皆様も少し気になっていると思うので、前述した「三角バイパス法」の理論についてもう少し説明を加えようと思う。
正八面体を描く反作用ベクトルの三角形運動を分析すると、角運動の中心点から吹き出した中心磁束が全部で四つの行程を経て再び中心点に戻ってくる事が分かる。一本のベクトル・フォースがその四行程で直角三角形を描く理由から三角形運動と名付けているが、実際には角運動の基盤運動である四角形運動と同じ四行程別の運動をしている。1本のダイレクト・フォースが描く平面的な四角形運動に対して、その4本のベクトル・フォースはそれぞれ四行程を経由して直角三角形を描き、正八面体の立体像(力の場)を生み出す。
図 19 (三角形運動の詳細図)
このベクトル・フォースの三角形運動を操作し、零磁場の小三角形運動の様なピラミッド(四角錐)を描かせると、ベクトル・フォースは北半球のみで循環し、南半球には降りて来ないという現象が起こる。つまり、大循環(八面体)させずに小循環(四角錐)させると、その余剰エネルギーを取り出す事が出来るのである。その理由は、大循環には四行程を費やすが、小循環には三行程しか費やさないからであって、1本のベクトル・フォースで“一行程分”の余剰エネルギーを抽出出来るからである。
半径がrの角運動を例に挙げると、この三角バイパス法で得られる余剰ベクトル・フォースは1回転につき4rであり、それは直径が30cmの円運動から1回転当たり60cmの推進力が得られるという意味である。一聞すると、小さな値の様に思えるかもしれぬが、回転するのは光速の磁束であり、1秒間で3億回転すれば一体どの位の距離になるのか想像が付くであろう。しかもこれは加速度なのである。こんな無限の永久駆動力が磁場の中に眠っているのに、それを利用しない手は無い。
では一体どの様な方法を使用すれば、回転磁場のベクトル・フォースを実際に取り出す事が出来るのだろうか。そのヒントは磁場の中に、ある物体を入れてベクトル・フォースの道筋を改めて作ってやる事であり、それを南下させない事である。ここまで説明すればもうピンと来る方も多い筈である。この三角バイパス法がUFOの駆動エンジンとして広く使用されている事実は一般に知られている通りである。回転磁場の半径と同じ直角三角形の1枚の金属板を入れるだけで、ベクトル・フォースの南下は防げるのである。
永久駆動力を磁場から引き出そうという未来技術は大変に魅力的なものである。なぜなら、宇宙船に今の燃料エンジンを積んで航海する事が出来ないからである。現在の地球型の宇宙船(垂直ロケット)では隣の星に行き着く事も出来ないばかりか、船内重力が無いそれでは人間は3年も生きられない。ましてや我々人類は、重力を断ち切る方法も知らず、またそれを制御する方法も知らない。癌の治療法も未だに分からなければ、無機物から有機物を作る方法も知らないのである。地球科学は進んでいるのではなく、反対に酷く遅れている事を認識しなければならないだろう。
我々が今研究しているものは、地球人類が将来、宇宙で生存していく為に必要な道具と知恵であり、その科学技術と科学知識を研究している。反重力磁界を生みだす「D-tube」や永久電流を生み出す「π-tube」、そして永久駆動力を生み出す「TAB-engine」など、あるいはレーザー増幅器や対衛星用波動砲など、魅惑的な未来科学の研究課題が我々には沢山あるが、残念ながら理論は完成しているものの、それを理解し実践してくれる技術者の仲間の頭数が足りない。またその研究に資本を提供してくれる企業も無ければ、国家の応援も無いというのが正直な所である。今回の発表は、この理論をより広く知ってもらう為のものであり、また、今取り組んでいる研究に国家的規模の経済支援と大規模な人員協力を頂きたいからである。つまり、船内重力を備えた超光速宇宙船を建造する為の国際的な研究機関を立ち上げて頂きたいというのが我々の望みである。
無論、今の科学理論の間違いを是正して、地球科学を根本から変革したいと考えているが、私自身は科学理論の訂正に生涯をかけるつもりは無い。真理は必ず受け入れられるものであって、遅かれ早かれいずれの日か念願が成就する日がきっと来ると信じているからである。それを待っているぐらいなら、先へ先へと進んで未来技術を確かなものにした方が良い。所詮、理論は理論に過ぎなく、それには土台的な価値しか無い。本当の価値と意義を持つものは科学的な発明であり、理論の具体的な応用実践である。癌の根本原因を見出しても、それを治す治療器や薬を作れなかったら原因を見つけた意味も価値も無い。我々はその様に考え、その様に実践している。

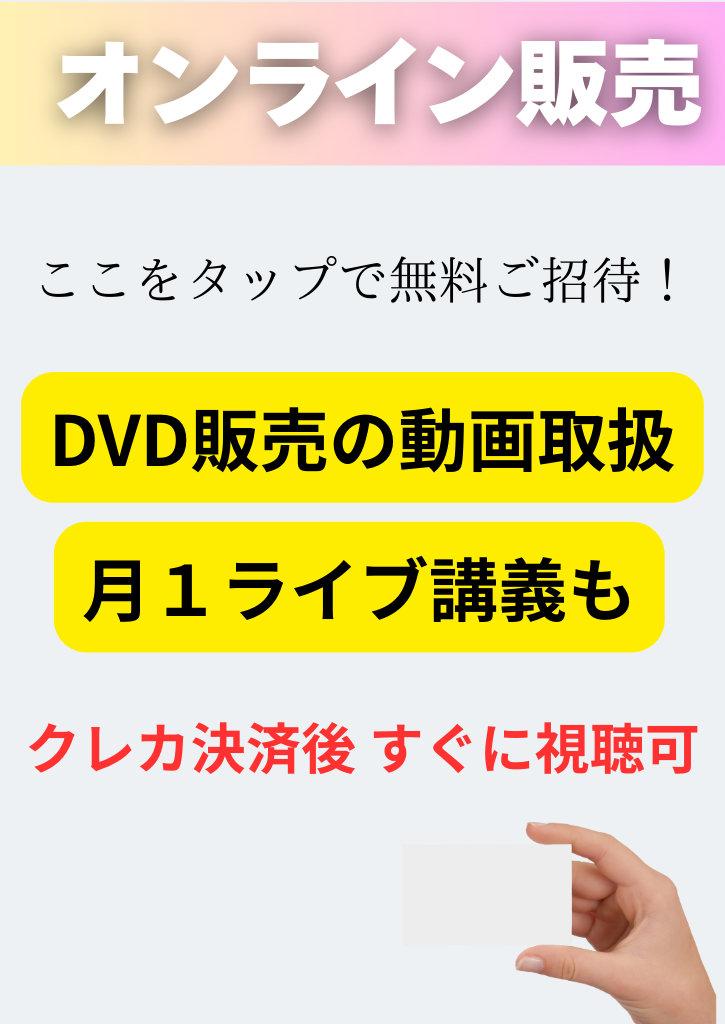





Comments are closed